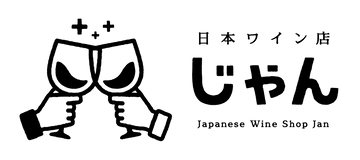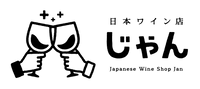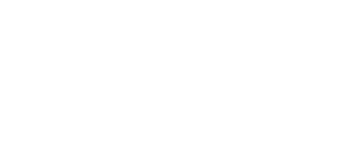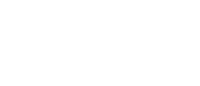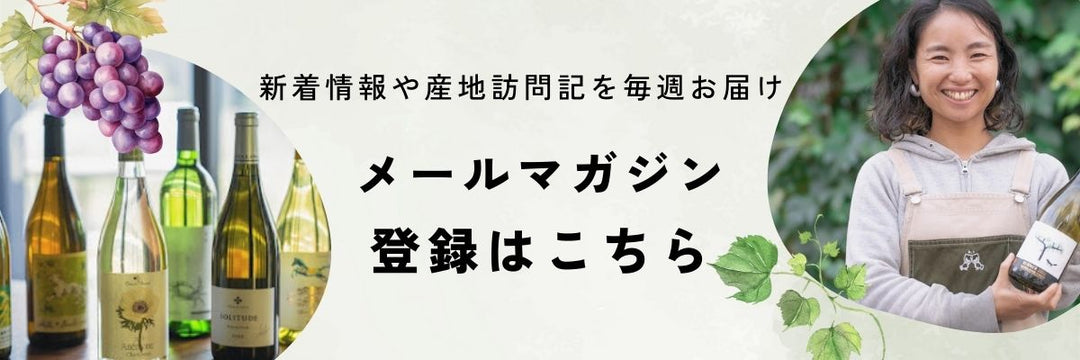シュールリー製法とは?日本ワインは甲州シュールリーが旨い!
「シュールリー」という言葉を聞いたことはありますか?甲州ワインには「甲州シュールリー」とラベルに大きく記載されているものも多いため、日本ワイン好きの方は目にしたことがあるかもしれません。シュールリーはワインの熟成方法の一つで、ワインに旨味や新たな風味を加え、より複雑で深みのある味わいを引き出します。今回はシュールリー製法について、その仕組みや特徴を詳しく解説していきます。
目次
シュールリーはどんな製法?

「シュールリー」はワイン製造における熟成方法の一つ。フランス語で「sur lie(澱の上)」という通り、通常取り除かれる澱(おり)と呼ばれる沈殿物をワインに残した状態で熟成させる手法です。特に白ワインやスパークリングワインの製造で用いられ、香りや味わいに独特のニュアンスを加えます。
ワインの主な製造工程は以下の通りです。
- 工程① ブドウの実を破砕・圧縮し、果汁を絞る
- 工程② 取り出した果汁をアルコール発酵させる
- 工程③ 発酵が終わったら、木樽やタンクに移して熟成させる
- 工程④ 濾過して澱や濁りを取り除き、瓶に詰める。栓をしたら完成
シュールリーは工程③の熟成工程の一環として行われます。 通常は工程②の発酵後に澱を除去し、澱がない状態で工程③の熟成を行います。
澱を除去する工程は「澱引き(ラッキング)」と呼ばれますが、この工程は雑味を除去して風味を安定させるとともに、ワインの透明度を向上させるために行います。シュールリーはこの澱引きをあえて行わず澱を残すことで、その風味成分をワインに吸収させ、味わいに複雑さや深みを与えます。
澱由来の成分は抗酸化作用を持つことがあり保存性の向上にも寄与します。ただし、栄養分が多く雑菌が繁殖しやすいため、温度管理が非常に重要です。
澱って何?

「澱」の正体は、ワインに含まれるタンニンやポリフェノール、タンパク質です。ワインが発酵や熟成する過程で、これらの成分が空気となじみ結晶化したものが時間と共に徐々に沈殿し、茶色や黒色の固形物として現れます。澱は、ワインの風味や味わい、テクスチャに影響を与える熟成における重要な要素です。上手く利用することで、ワインの品質を高め、より複雑でバランスの取れた味わいを生み出す鍵となります。(詳しくは:ワインの底に溜まっているカスって何?「澱」の正体とおいしく飲む方法 )
シュールリーがもたらす香りと味わい

シュールリー製法では、アルコール発酵終了後、タンクや樽の底に沈殿した澱を時々攪拌しながら数か月に渡って漬け込むことで酵母の風味を移します。発酵後の澱(酵母)は自己分解してアミノ酸や多糖類などに変化し、ワインに旨味として溶け込みます。この現象はオートリシスと呼ばれます。
酵母由来の分解物質は、ワインにナッツやパンの皮のような香りをもたらします。また、酸味のバランスも調整してくれるため、口当たりがクリーミーで柔らかい質感になります。
そのため、シュールリー製法を用いた白ワインはただ軽快なだけでなく、爽やかながらクリーミーでリッチ感のある口当たりで、うま味や複雑な風味を感じることができます。スパークリングワインでは、柑橘系に例えられるフローラルなアロマに加え、ナッツのような香ばしい香りが増します。
シュールリーにおける攪拌の役割
シュールリー熟成中、澱が容器の底に沈んだままだと効果が部分的になったり、ワインの重さでつぶれてしまったりします。これを防ぐために、定期的に攪拌を行い、澱をワイン全体に均等に分散、浮遊させます。この作業をバトナージュといいます。
バトナージュは、澱の成分をより効率的にワインに取り込むために行われ、シュールリー熟成の効果を最大化します。ただし、頻度や方法を誤ると澱が不快な香りや味を発するリスクもあるため、慎重に行う必要があります。攪拌するのに用いられる方法は、攪拌棒を使ってかき混ぜたり、大量の酸素を送り込んでかき混ぜるなど、つくり手によって様々です。
シュールリーの期間

シュールリーによる熟成は一般的に6ヶ月以上ですが、期間は目指すスタイルやその他の条件によって幅があります。フルーティーで軽やかなスタイルを目指す場合は数ヶ月ですが、複雑な風味やよりリッチなテクスチャを求める場合は1年以上の長期間に及びます。最上級のものになると、シュールリーだけで3年以上かけているものもあります。熟成期間は、ブドウの品種や熟成環境(保管温度や容器の種類)、攪拌の頻度といった条件にも影響されます。
ワイン製造はブドウの収穫が行われる秋に始まることが多いため、シュールリーによる熟成が開始されるのは秋から冬の時期にかけてです。この時期の低温環境は、酵母の分解が進みやすく、ワインに効果的な風味を加えるのに適しています。
シュールリーは赤ワインでは行わない?

シュールリーは主に白ワインやシャンパンで行う製法で、赤ワインで行われることはほとんどありません。その理由は、赤ワインの製造過程やスタイルの違いに関係しています。
● タンニンの存在
赤ワインはブドウの皮や種子から抽出された豊富なタンニンが、渋みや重厚感を構成する要素となります。シュールリーによる熟成は滑らかさやクリーミーさを増しますが、タンニンが強い赤ワインではすでに味わいに深みや構造があるため、その効果はあまり期待されません。
● 求められる風味の違い
赤ワインは主に果実味、スパイス、そしてオーク樽熟成によるスモーキーな香りなどが伝統的な風味の特徴です。シュールリーを行うとナッツやパンの皮のような香りを強調するため、赤ワインの伝統的なスタイルとはあまり合致しません。
● 赤ワインの製造工程
赤ワインは発酵中に皮や種子と一緒に浸漬する「マセラシオン」工程を経ることで、濃厚な色合いやタンニンを得ます。このプロセスでは澱が発酵後に除去されることが一般的であるため、シュールリーと両立することは難しくなります。
赤ワインの豊かなタンニンや果実味を重視した伝統的な製法に対し、シュールリーは白ワイン特有の滑らかさや香りを引き立てるために用いられることが多い点がポイントです。ワインの個性を際立たせるために、たくさんある製法の中からそれぞれのワインに最適な方法が選択されているということです。
シュールリーと無濾過の違い

「澱引きせずに熟成を行うということは、無濾過ワインということ?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。シュールリーと無濾過はどちらも澱が関係していますが、それぞれ異なる目的を持って行われています。
シュールリーは熟成技術であり、澱を活用して風味や質感を向上させます。ワインの安定性を向上させ、見た目をクリアに整えるために、最終的には濾過を行ってから瓶詰めをすることが多いです。澱の成分は溶け込んでいるので、濾過を行ってもシュールリー特有の風味や質感は保たれます。
一方で、無濾過は濾過の工程を省略することで、ワインをより自然な状態に保つことを重視しています。瓶詰め時にも澱を残すことで、ワインの自然な風味を保存し、ブドウ本来の特徴を最大限に表現します。その結果、生き生きとした力強い味わいとなり、見た目は濁りが発生する場合もあります。(詳しくは:無濾過ワインとは? )
シュールリーが用いられる代表的なワイン

シュールリーは世界中で使われている手法ですが、最も有名なのはフランスのロワール地方の「ミュスカデ」です。その昔、ブルゴーニュからやってきた品種のため、別名(ワイン用語ではシノニム)を「ムロン・ド・ブルゴーニュ」ともいいます。ミュスカデは辛口で爽やかな風味の軽快なワインを作る、白ワイン用のブドウ品種ですが、シュール・リー製法で造られたミュスカデは、爽やかながらもほんのり旨味を感じる味わいになります。
他には、フランスのシャンパーニュ地方で造られるスパークリングワインや、アメリカのカリフォルニアでは主にシャルドネを中心にシュールリー製法が取り入れられています。シャルドネやシャブリはフルーティーで洗練された味わいが魅力です。シャンパンやクレマン・ド・ブルゴーニュなどのスパークリングワインでは、シュール・リー製法により繊細な泡立ちと複雑な風味が実現されます。日本では、山梨県の甲州で多く使用されています。ちなみに、甲州は日本の固有品種であるため別名(シノニム)はなく、海外でも「Koshu」と表記されます。
日本ワインでは甲州がおすすめ!
シュールリーを用いたワインで、日本ワインでは「甲州ワイン」がおすすめです。(詳しくは:日本ワインで良く聞く「甲州」の正体を解説! )
甲州ワインはさっぱりとした軽やかな仕上がりが特徴で、刺身や野菜料理などの日本食と非常に相性が良いです。特にシュールリー製法を採用した甲州ワインでは、ふっくらとしたコクと旨味が強化され、その豊かな味わいが際立ちます。お鍋の出汁や餃子の肉汁など、旨味の強い料理と合わせるのもおすすめです。
● ロリアン勝沼甲州
創業から80年以上の歴史を持ち、勝沼の地元農家と共に歩んできた老舗ワイナリーが手掛ける甲州のフラッグシップワインです。「ロリアン」という名前はフランス語で「東洋」を意味し、日本らしさと勝沼らしさを追求したこのワインは、和食との相性がよいと評判です。世界のワインコンクールで輝かしい受賞歴を誇り、漫画「美味しんぼ」で紹介され一躍有名になりました。シュールリー製法で造られたこのふくよかな白ワインは、コクと旨味が特徴で、深い風味をたのしむことができます。

漫画「美味しんぼ」掲載の、老舗ワイナリーの作るフラッグシップワイン。旨味がたっぷり、当店のスタメン商品です!
● かざま甲州シュールリー
日本で一番甲州ワインを上手く作る男と称される、甲斐ワイナリーの風間さんによるシュールリーの甲州ワイン。甲斐の地に根付き伝統を守りながらも常に新しい挑戦を続けるこのワイナリーは、日常に寄り添う繊細で豊かな味わいを提供してくれます。シュールリーの名を冠したこのワインは、特に出汁+醤油の組み合わせとの相性が抜群で、和食とのペアリングを楽しむのに最適です。

キレと旨味が共存する、上品で爽やかな辛口白ワイン。肩の力が抜ける心地よさとごくごく飲めるおいしさ
シュールリー製法のワインが持つ独特の風味と深みを体験して、あなたのワインライフに新しい発見を加えてみてください!
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。