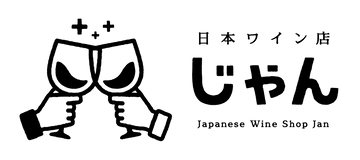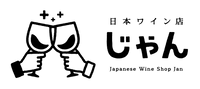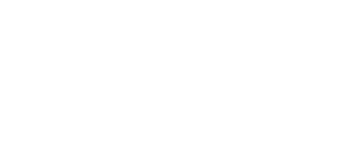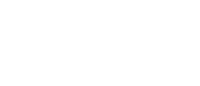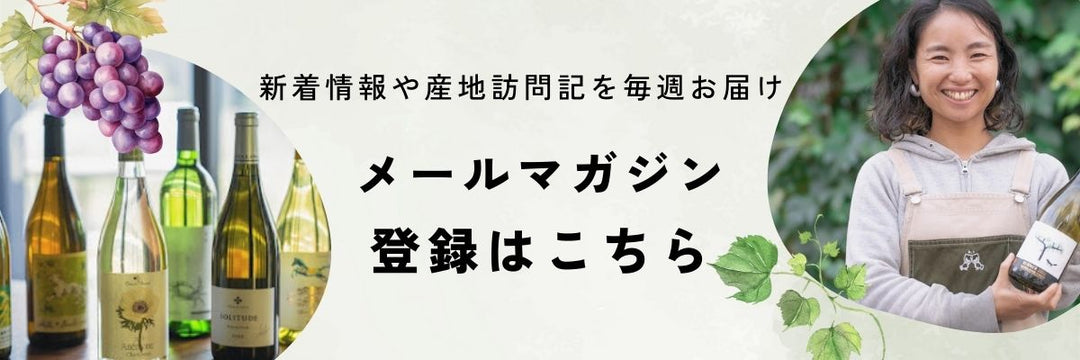ワインの製法「マロラクティック発酵」について説明
ワインのラベルの裏の説明の中に「マロラクティック発酵(MLF)」という言葉を見かけることがあります。ワイン製造過程で重要な役割を果たす二次発酵の一種、マロラクティック発酵について説明します。
目次
マロラクティック発酵(MLF)とは?
マロラクティック発酵(Malolactic Fermentation)は、ワインが初期のアルコール発酵を終えた後に、リンゴ酸を乳酸と二酸化炭素(炭酸ガス)に変える微生物による発酵プロセスです。この発酵は通常、ワインの軟らかさと風味を向上させるために行われます。
アルコール発酵は、「酵母」の力でブドウの「糖」を「アルコール」に変えますが、マロラクティック発酵は、「乳酸菌」の力で、ブドウのもろみに含まれる「リンゴ酸」が「乳酸」に変化する発酵のことです。
マロラクティック発酵(MLF)で作られたワインの特徴は?
マロラクティック発酵(MLF)で作られたワインにはいくつかの特徴があります。
軟らかな酸味
MLFにより、リンゴ酸が乳酸に変わるため、ワインの酸味が軟らかくなります。これにより、ワインが滑らかで飲みやすくなります。
風味と複雑性
MLFはワインに新たな風味と複雑性をもたらし、バターやクリームのニュアンスを持つことがあります。これは特にシャルドネなどの白ワインに見られます。
微生物の働き
MLFには、乳酸菌が関与します。これらの微生物は、ワインの品質を改善し、不要な化合物を減少させます。そのためワインの安定性が向上し、長期間の熟成に適している場合があります。
ワインのラベルにマロラクティック発酵(MLF)の記載がないか見てみましょう
いかがでしたか?「マロラクティック発酵(MLF)」の文字をラベル裏の説明に見かけたら、つくり手の方がどんなワインを作りたかったのか想像するヒントになりそうですね。
More from:
豆知識