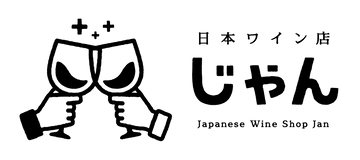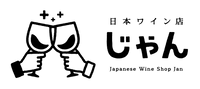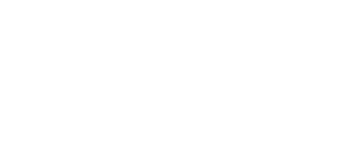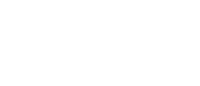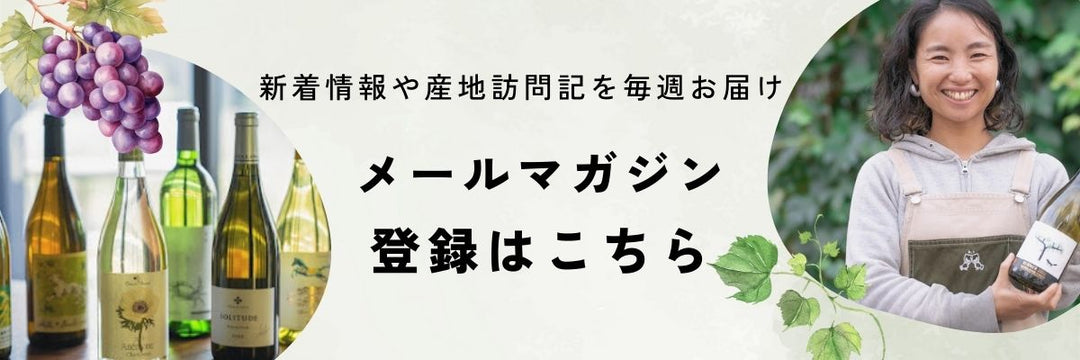ワインの底に溜まっているカスって何?「澱」の正体とおいしく飲む方法
ワインの瓶の底に溜まっているカス、この正体は「澱」と呼ばれる沈殿物。製造過程で自然に発生する、ワインの成分が結晶化したものです。
澱は、熟成を経て生まれる貴重な成分であり、ワインの味わいに深みや複雑さを与える重要な要素です。
今回は、澱の正体や澱と熟成の関係、おいしく飲む方法についてレクチャーします。
また、澱があるからこそおいしい、日本のワイナリーで造られたこだわりのワインについてもご紹介します!
目次
ワインの瓶の底に沈殿している「カス」の正体は?
ワインの底に溜まる沈殿物には種類があり、「カス」と呼ばれる沈殿物は「澱(おり)」、キラキラ輝いてみえる結晶は「酒石(しゅせき)」といいます。
これらは製造過程で自然に発生するワインの成分が結晶化したもので、飲んでも問題はありません。むしろ、単なる副産物ではなくワインの個性や風味を
形作る重要な要素なのです。
澱や酒石について知ると、ワインの品質や製造過程についての知識が深まり、自分がどんなワインを飲んでいるのか、そのワインがどう作られたかを知る
手がかりにもなります。ワインの選び方や楽しみ方がさらに深まること間違いなしです。
ワインの成分が沈殿した「澱(おり)」

「澱」の正体は、ワインに含まれるタンニンやポリフェノール、タンパク質です。ワインが発酵や熟成する過程で空気となじみ結晶化したものが、時間と共に徐々に沈殿し、茶色や黒色の固形物として現れます。この中には醸造の過程で発生する、ブドウの皮や種、果肉の欠片や酵母の残留物も含まれています。
澱が発生するプロセスには時間がかかるため、澱が多く残っている=ワインが瓶内で長期間熟成された証と考えられます。
見た目や口当たりに影響するので、ワインメーカーでは澱を取り除く工程を経るのが一般的ですが、ワイン本来の風味や香りを楽しむためのフィルタリングや濾過を行わない製法のワインもあります。(詳しくは 「ワインの無濾過ってどういうこと?」 )
キラキラした結晶は「酒石(しゅせき)」

酒石は、透明または白色の結晶で、ブドウに含まれる「酒石酸」と「カリウム」が結びついてできたものです。ワインが低温で貯蔵されたり、
冷却されたりすると生じます。見た目のみで味にはほとんど影響はありません。
酒石の存在は、酸やミネラル分を多く含む質の良いワインであるという指標でもあります。白ワインの酒石は光に当たるとキラキラ輝いて見えることから、「ワインのダイヤモンド」とも言われています。
澱と熟成の関係

澱はワインの熟成には欠かせない要素です。適切に管理することで、ワインの品質を高め、より複雑でバランスの取れた味わいが生まれます。
ワインに含まれる澱からはアミノ酸や酵母由来の成分が溶け出し、ワインに複雑な香りや風味を加えます。
また、ワインに含まれる酸素を吸収して酸化を防ぐので、酸化による劣化を抑え長期間に及ぶ熟成が可能になります。
さらに、澱との接触によってワインのテクスチャーが滑らかになり、口当たりも改善されます。特に白ワインは澱と接触することで、よりリッチでクリーミーな口当たりが実現します。このような理由から、澱を重視するワイン愛好家も多くいます。時間をかけてじっくりと熟成された味わいはとても贅沢なものです。
ただし、輸送や保存の際の状態が悪く、ワインが酸化して澱が発生するケースもあります。酸化が原因で発生した澱は粒子が粗く不均一です。
また、適切に保管されたワインは、澱がしっかり沈殿した状態でワインセラーで熟成されるため、ボトルの片面にしか澱が付着していないという特徴があります。ワインを選ぶ際には、こうした点も参考にしてみてください。
ワインの品質を高める工程「澱引き」
ワインの製造過程では、澱を取り除く「澱引き」という工程があります。澱を取り除くことによって、雑味を除去して風味を安定させ、
同時にワインの清澄度を向上させます。
しかし、澱引きで全ての澱を完全に取りきるのは難しく、熟成の過程や保存状態によっては再び澱が形成されることもあります。
そのため、澱引きを行ったワインでも澱が残っていることはあります。その場合は、澱がグラスに入らないようにして飲むのが良いでしょう。
「赤ワインの澱」と「白ワインの澱」の特徴と発生理由は?

澱はヴィンテージの上質な赤ワインでよくみられる印象ですが、白ワインや若い赤ワインにも発生することがあります。澱が発生するのはどのようなワインなのでしょうか?
● タンニンが多い赤ワイン
澱の素であるタンニンを多く含んでいると、澱は発生しやすくなります。よくみられるのは赤ワインの中でもフルボディのワインで、
品種は「カベルネ・ソーヴィニヨン」「シラー」「ネッビオーロ」「タナ」など。味わいや香りが豊かで、アルコール度数は高めなのが特徴です。
口に含んだときにしっかりとした存在感があり、重厚な印象を持たせます。
● 長期熟成ワイン
熟成が進み、酵母や微生物が分解されることでも澱は発生します。そのため、長期間熟成された古いワインに多く含まれることがあります。
長期熟成された赤ワインは、渋味が和らぎ、まろやかさとコクのある味わいになります。
● ナチュラルワイン
ナチュラルワインは自然な製造方法を重視するため、澱は取り除かないのが一般的です。フィルタリングを最小限に抑えるので、熟成が浅いものでも
澱が生じることがあります。添加物を使用しておらず、ブドウ本来の味わいを楽しむことができます。
● 未濾過ワイン、無濾過ワイン
未濾過ワインは一定の濾過が施されていますが、無濾過ワインは一切の濾過を行いません。濾過を行わないことで果実や酵母の残留物が多く残り、澱が発生しやすくなっています。どちらも自然な風味と個性がありますが、無濾過ワインはより複雑さ力強さを味わうことができます。
これらのワインには澱が含まれている可能性が高いため、飲む前に取り除く準備をしておくと良いでしょう。
「澱が回る」とは?澱のあるワインの扱い方
「澱が回る」という表現は、沈殿していた澱が舞って瓶全体に広がってしまうことを指します。ワインの見た目や口当たりに影響が出てしまうため、避けることが望ましいです。瓶を運ぶ際やワインを注ぐ際のちょっとした振動で広がってしまうので、澱のあるワインは慎重に取り扱うようにしましょう。
澱を取り除く「デキャンタージュ」とは?

澱はワインに含まれる自然な成分が熟成過程で結晶化したものなので、そのまま飲んでも問題はありません。
しかし、えぐみや渋みがあり口当たりも悪くなるため、ワイン本来のおいしさを損なわないためには、取り除いてから飲むことをおすすめします。
まずワインを開ける前に、縦置きにした状態で数時間から数日間動かさずに保管し、澱が自然にボトルの底に沈殿するのを待ちます。沈殿したかどうかは
目視で確認してみてください。コルクを抜く際は、せっかく沈殿した澱が舞ってしまわないよう、できるだけ動かさずにそっと抜いてください。
この後に行うのが、「デキャンタージュ」という方法です。これを行うことで澱がグラスに入るのを防ぎます。
デキャンタージュは、デキャンタというガラス容器にワインの上澄みをゆっくり注いで澱を取り除きます。ワインは空気に触れた瞬間から酸化が進み、
風味が損なわれてしまうことがあるので、デキャンタに移し入れる前にテイスティングしておくのがおすすめです。
ご自宅にデキャンタがない場合は、目の細かい茶こしやワインストレイナーを使って取り除くこともできますよ。
澱とワインボトルの形状の関係

実はボトルの形状にも、澱が舞い上がらないようにする工夫があります。「Punt(プント)」と呼ばれるボトルの底にある大きなへこみは、ワインを注ぐ際に対流が発生して澱が舞い上がるのを防ぐためにあるとも言われています。(詳しくは「ワイン瓶底の凹みの理由は?」 )
おすすめの日本ワイン
今回紹介する日本ワインは、北海道余市町にある平川ワイナリーのワインです。品種非公開で作られたこだわりのワインは、どのアイテムにも綺麗な酒石がキラキラとしていてため息が出るほどの美しさです。
作り手の平川さんは、22歳で単身フランスに渡りワインづくりを学ばれています。帰国後は一流ホテルやレストランでソムリエとして活躍され、
現在は「日本の美食文化に合うワインをつくる」ことを目指して、自らワイナリーを設立されています。
とっておきのワインや贈り物に、ダイヤモンド付のワインはいかがでしょうか。
まとめ

今回は、澱の正体や発生する理由、澱と熟成の関係、澱のあるワインのおいしい飲み方について解説していきました。
ワインの澱は熟成を経て生まれた貴重な成分であり、ワインに深みを与える重要な要素です。澱が発生しやすいワインやその取り扱い方について理解を
深めると、ワインの楽しみ方も一層広がります。
日本ワインにも素晴らしい澱を感じられるワインが多くあります。当店でも取り扱いがありますので、ぜひその味わいを試してみてください。
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と
感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。