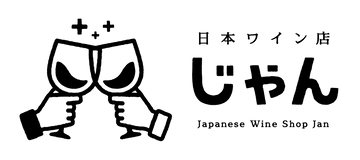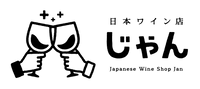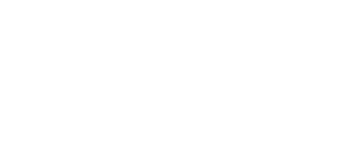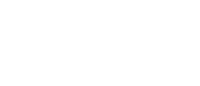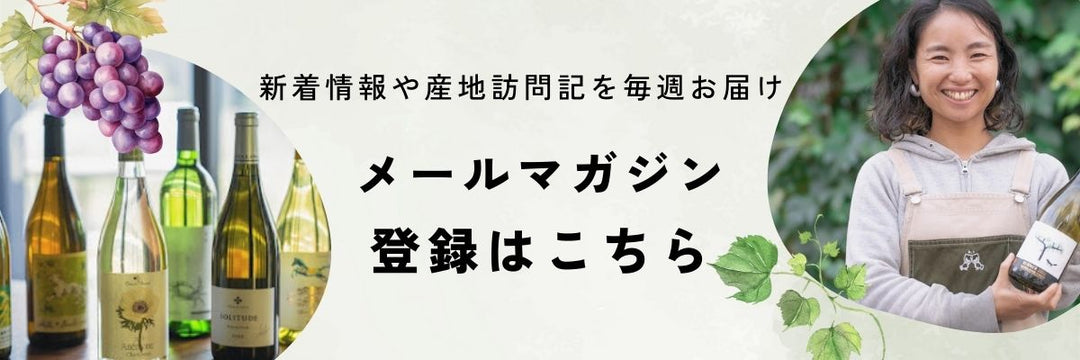ワインの野生酵母、培養酵母とは?その種類と役割を解説!
ワインは酵母の力でブドウ果汁を発酵させて作るお酒です。酵母はアルコールを生成するだけでなく、ワインの香りや味わい、質感にも大きな影響を与えます。さらに、使用する酵母の種類によって、個性が異なるのも特徴です。「野生酵母」と「培養酵母」は何が違うのでしょうか?この記事では酵母の役割や種類について詳しく解説します。
当店おすすめの野生酵母で造られた日本ワインもご紹介していますので、目で舌でその違いを感じてみて下さい。
目次
酵母って何?

酵母は真菌類の一種で、糖をアルコールや炭酸ガスに変えるはたらき(発酵)を持つ微生物です。果物の表面や土壌など自然界のいたるところに存在しているため、古代からさまざまな食品や飲料の製造に活用されてきました。目に見えないほど小さな生物ですが、人々の生活には欠かせない存在です。
酵母の種類はとても多く、自然界に数千ほど存在するとも言われています。ワインやビール、日本酒、焼酎などのアルコール飲料をはじめ、パン、チーズ、ヨーグルト、味噌などの発酵食品も、酵母のはたらきを利用して作られる食品です。
ワインづくりにおける酵母の役割

ワイン作りにおいて、酵母にはブドウを発酵させ、アルコールを生成する働きがあります。さらには香りや味わい、質感にも大きな影響を与えます。
酵母の役割① アルコール発酵
ワインづくりにおける、酵母の最も重要な役割は「アルコール発酵」です。ワインは以下のような工程を経て作られます。
- 工程① ブドウの実を破砕・圧縮し、果汁を絞る
- 工程② 取り出した果汁をアルコール発酵させる
- 工程③ 発酵が終わったら、木樽やタンクに移して熟成させる
- 工程④ 濾過して澱や濁りを取り除き、瓶に詰める。栓をしたら完成
工程②の「アルコール発酵」では、酵母を加えてブドウ果汁に含まれる糖分を分解、炭酸ガスとアルコールを生成します。この時発生した炭酸ガスは発酵の途中で放出されます。
役割② 風味とアロマの形成
発酵の過程で、酵母はアルコールだけでなく、ワインの風味や香りを決定づける化合物を生成します。酵母の種類や製造環境によって、生成される物質やその量は異なり、ワインの個性や特徴に大きな影響を与えます。
役割③ テクスチャへの影響
発酵後、酵母が分解されると、ワインの質感に「まろやかさ」や「なめらかさ」が加わり、口当たりが柔らかくなります。この変化は特にスパークリングワインにおいて顕著で、リッチな飲み心地を楽しむことができます。
役割④ 保存性の向上
発酵中に酵母が酸素を消費することで果汁の酸化が防げ、ワインの品質が安定するとともに、保存性が向上します。
ワインの味わいはブドウの品種や質によって基本的な骨格が決まりますが、酵母のはたらきも個性の形成に大きく関わっているのです。
野生酵母と培養酵母の違い
ワインづくりでは、作り手の哲学や目指すワインのスタイルによって「野生酵母(自然酵母、天然酵母)」や「培養酵母」について語られることがあります。
「野生酵母」はブドウに付着した天然の酵母のことです。一方で「培養酵母」は特定の特徴や性質をもつ酵母を増殖培養したものです。それぞれに異なる良さがあり、どちらを選ぶかは作り手の考え方によります。
野生酵母とは?

野生酵母はブドウの生育地ならではの特徴を持つため、テロワールが強く反映され、風味に独自性が生まれます。そのため、同じブドウ品種でも産地によって全く異なる味わいを楽しむことができます。(詳しくは:テロワールとは? )
ブドウ果実の表面に付着しているため、果実が潰されると自然と発酵が始まりますが、それだけでは良いワインはできません。酵母のはたらきをいかにコントロールするかが、良いワインを作るカギとなります。
野生酵母で発酵させたワインには、魅力的な要素がたくさんあります。
魅力ポイント① 豊かな風味とアロマ
果実味と自然な酸味のバランスが良く、深いアロマが楽しめます。
魅力ポイント② 添加物が少ない
人工的な添加物や保存料である亜硫酸塩の使用を最小限に抑える場合が多く、より純粋な味わいを堪能することができます。
魅力ポイント③ 発酵の複雑性
野生酵母発酵では複数種類の酵母が混在することがあり、発酵がより複雑になります。これが独自の香りや味わいを生み出します。
一方で、ワインに適さない雑菌が混ざったり発酵が不安定で管理が難しいという製造上のリスクもあります。
培養酵母とは?

培養酵母は、ワイン造りに適した性質を持つ酵母を培養したもので、これをブドウ果汁が入ったタンクに加えて発酵を行います。培養する酵母は、発酵力、味わいや風味、生産管理のしやすさを考慮して選ばれており、安定した品質のワインを作りやすくなります。
魅力ポイント① 品質を安定させる
培養酵母は、それ自体の品質が安定しているため、発酵が途中で止まったり、雑菌が繁殖するといったリスクが低く、品質が安定しやすくなります。
魅力ポイント②自由度の高さ
酵母の持つ異なる特性を生かして、アルコール度数や発酵速度をコントロールすることが可能です。活発にはたらく酵母を使って発酵速度を速めると、効率よく発酵が進み、生産性の向上に寄与します。
また、特定の香りや風味を引き出すものもあり、花のような香りやフルーティーな風味を際立たせる酵母などを選べば、ブドウ品種の特徴を活かしたワインを作ることができます。このように、目指すワインのスタイルに合わせて酵母を選べるため、ワインの個性をつくり手がデザインできるのです。
魅力ポイント③ 保存性の高さ
雑菌が混じりにくいため、予期せぬ発酵や腐敗を回避でき、保存性が向上します。
一方で、野生酵母と比べると風味がやや画一的で、テロワールの影響が弱まる傾向にあるため、野生酵母を併用するなどの工夫をする場合もあります。
培養酵母がワインづくりに使われ始めたのは、生化学の発展により酵母の役割や発酵の仕組みが科学的に解明された19世紀後半から20世紀初頭です。フランスの科学者ルイ・パスツールがアルコール発酵における酵母の重要性を発見したことが、培養酵母の利用を促進するきっかけとなりました。培養酵母の導入は、ワインづくりの効率化と品質の安定化に大きく貢献し、大量生産を可能にしました。量産型ワインに限らず、高品質なワインの製造にも活用されています。
酵母のはたらきを調整することの重要性
酵母の働きをコントロールすることはワインづくりにおいて非常に重要です。発酵の進行速度、酸素供給、栄養管理などを適切に調整することで、ワインの品質を高めてくれるからです。野生酵母を使ったワインづくりはとても繊細で、発酵の不確実性や微生物の影響を考慮しながら進める必要があるため、発酵の進行状況を見極め、必要に応じて調整する技術が求められます。
● 発酵の速度と温度管理
温度は発酵速度に影響し、生成される香りや風味に作用します。高温で発酵を進めると強い香りが引き出され、逆に低温でゆっくりと発酵させると、より繊細で穏やかな風味が生まれます。
● 酸素供給・栄養素の補充の調整
発酵中の酸素量、pH、栄養素のバランスは酵母の活性に影響を与えます。これらは適切に管理すると、発酵を安定させ、望む風味を引き出すことができます。酵母が不安定になると、発酵が途中で停止したり、不快な風味が生じる原因となります。
● 微生物の管理
発酵中にタンク内で細菌が繁殖してしまうと、ワインの風味が悪くなり、品質が低下する原因になります。
● 発酵終了後の管理
発酵終了後も酵母の働きは続きます。酵母細胞が含まれる澱を残したままだと風味に影響を与えるため、ワインを清澄して取り除きます。ただし、澱を残すことで、より豊かな風味を引き出すことも可能です。
野生酵母を使う日本のワイナリー
<ココ・ファーム・ワイナリー(栃木県)>
日本にも野生酵母からつくられたワインはたくさんあります。その代表的なワイナリーのひとつが、栃木県にあるココ・ファーム・ワイナリー。野生酵母で発酵させるワインづくりを早くから取り入れ、日本ワイン界で自然派ワインを牽引してきた存在です。

ココ・ファーム・ワイナリー以外にも、こちらのつくり手も野生酵母を使ったワインづくりをされています。
<グラン・ミュール(長野県)>
長野県小諸市の千曲川ワインバレーに農地を有するヴィンヤードさん。
家庭の和食に合うワインを追求しながら、野生酵母醸造でワインづくりをされています。
様々な品種のブドウを栽培されていますが、特に力を入れているのが日本では珍しいスイス原産の「シャスラ」というブドウ品種。生産者の川口さんは「和食に最も合うのはシャスラ」と語ります。このシャスラとピノグリを使用したスパークリングワイン「奴隷の分け前」は当店でも人気の商品。クリアな味わいの中にしっかりとした果実味が感じられるのが魅力です。


喉の奥にグっと来る濃い果実味と、きめ細やかな泡立ち!
ホタテのオイル漬けや白身魚のバターソテーと相性抜群
<ミリ・ボーテ(長野県)>
同じく、長野県小諸市に位置する「ミリ・ボーテ」。浅間山のふもと、千曲川沿いの自然豊かな菱野地区に畑とショップを構えており、千曲川が生み出す雄大な自然の美しさをワインを通じて表現されています。
ミリ・ボーテでは、ブドウの品種特性や土地の個性を最大限に引き出すため、複数品種のブレンドではなく単一品種で仕込むスタイルを採用。標高の高さと冷涼な気候を活かしたワインは、熟した果実味と綺麗な酸味のバランスが特徴です。フラグシップである「カベルネフラン」は、手除梗したブドウを野生酵母で発酵させた後、フレンチオーク古樽で6ヶ月熟成した無添加・無濾過の辛口赤ワインで、完熟した旨味と酸味のバランスが特徴の洗練された味わいです。


木の皮のような青い香りがあり、果実味豊かでエレガントな味わい
まとめ
酵母はワインづくりで欠かせない存在であり、その種類や使い方によってワインの味わいや香りに大きな影響を与えます。そのため、酵母の選定や管理は作り手の技術や意図によって左右される重要な要素となります。特に野生酵母は、地域性やブドウ品種の特徴を引き出し、ユニークで個性豊かなワインを生み出します。飲む時にはその個性も気にしてみて下さい。
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。