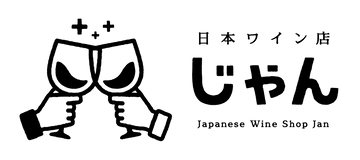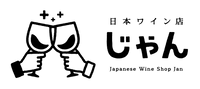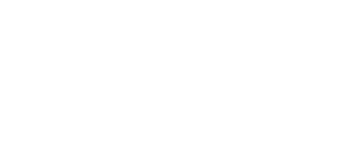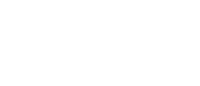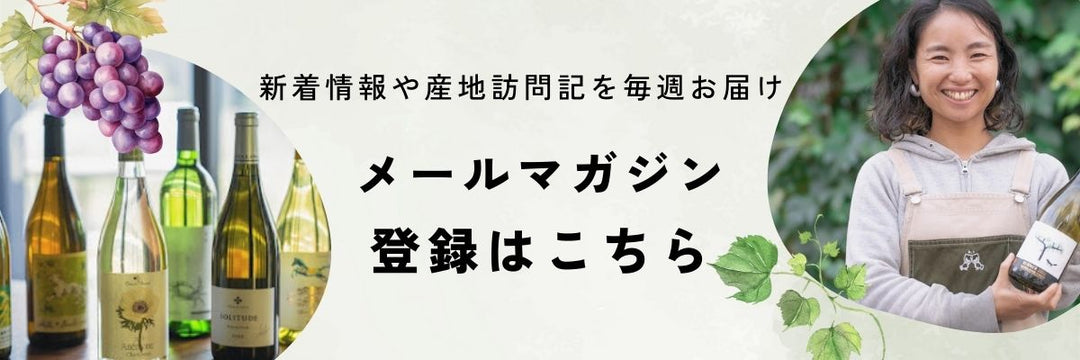ワインボトルを解説!容量や種類から、瓶底の凹みの役割も
普段何気なく手に取っているワインのボトル。さまざまな形や色があり、それぞれに意味や役割があることをご存じでしょうか。
またそのデザインは、ワインの品質を保持し特性を引き出すための工夫が細部に施されています。
今回はワインボトルのデザインに焦点を当て、形や色の違いとその理由、瓶底の構造や容量に関するよくある疑問について解説します。
自分の好みのワインを選ぶヒントにしてみてください。
目次
ワインボトルの歴史
ワインボトルは最初から現在の形で作られていたわけではありません。ワインの歴史とともに、ワインボトルも時代によって進化してきました。
ワインが誕生したとされる紀元前6000年頃、ワインの製造・保存には、大型の粘土製の壺や陶器が使用されていました。代表的なものは、ジョージアの
「クヴェヴリ」、古代ギリシャ・ローマの「アンフォラ」と呼ばれる土器です。土器は重くて脆く、運搬中に破損しやすかったため、より軽くて丈夫な
オーク樽がこれに代わって登場します。
しかし、土器やオーク樽は長期の保存には向いておらず、酸素に触れて酸化しやすい、蒸発して中身が減ってしまうなどの弱点がありました。
現在のワインボトルに近い形態が登場したのは17世紀頃です。ガラス加工技術の発展によりガラス製容器が普及し始め、ワインの保存や輸送に適した形態が整っていきました。ガラス製のワインボトルはそれまでと比べてさらに丈夫になり、密閉性を高めるコルク栓と組み合わせることで、ワインを長期間保存・熟成させることが可能になりました。その結果、ワインの品質は劇的に向上し、何十年も熟成させたヴィンテージワインを楽しむこともできるようになったのです。
近年では、リサイクル素材で作られた軽量ボトルや、コルクの代用としてスクリューキャップが使われたりと、さらなる変化を見せています。
ワインボトルの形状の種類

ワインボトルにはさまざまな形状があり、それぞれのデザインに生産された地域やワインのタイプに関連した特徴があります。これらの特徴を知っておくと、ボトルを見るだけでどの地域のワインか、どんなワインなのかをある程度推測することができます。代表的なのは以下の5種です。
● ボルドー型
ワインの種類:カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ソーヴィニヨン・ブランなどのボルドーワイン
直線的で肩が張っている形状は「いかり肩」とも表現されます。ボルドーワインは、タンニンを多く含み、熟成すると澱が発生することが多くあります。
その澱を避けて飲むために、注ぐ際にボトルの肩部分に澱を留めることができるよう設計されています。そのため、ボルドー以外の地域で生産された
フルボディの赤ワインにも、ボルドー型が多く使われています。
● ブルゴーニュ型
ワインの種類:ピノ・ノワールやシャルドネなどのブルゴーニュワイン
ボルドーより太めで、肩の部分はなだらかな「なで肩」。ブルゴーニュ地方の貯蔵庫は狭かったため上下互い違いに収納しやすいように、繊細な味わいのワインを静かに注げるように、と諸説あるようです。
● シャンパン型
ワインの種類:シャンパンをはじめとするスパークリングワイン
炭酸ガスの圧力に耐えられるように、一般的なワインのボトルより分厚く頑丈に作られています。瓶底も厚く凹みは深めになっています。ブルゴーニュ型と似たなで肩形状ですが、全体が一回り大きく、ネックが長めでボトル下部が太くなっているのが特徴です。
● ライン型/モーゼル型/アルザス(フルート)型
ワインの種類:リースリングやゲヴュルツトラミネール、シルヴァーナーなどのドイツワイン、フランスアルザス地方のワイン
背が高くすっきりとした細身で、肩の部分はほとんどありません。細身の形状は、ワインが酸化しにくく香りを保ってくれるので、リースリングなどの
アロマティック品種に向いています。また、ボトルが冷えやすいという利点から、冷やして飲むことが多いワインに適しています。
フランスのアルザス地方はかつてドイツ領だったため、ドイツとほぼ同じ形状のボトルが使用されています。
● ボックスボイテル
ワインの種類:リースリング、ミュラー=トゥルガウ、シルヴァーナーなどのドイツ・フランケン地方のワイン
ボトルネックから下が円状に膨らんでいます。伝統的な形で一部地域でしか使うことを許されていません。18世紀、フランケン地方では粗悪なワインが蔓延していたため、醸造所で造ったワインと識別する目的で使用されたと言われています。ワインを長距離移動をさせるときに腰から下げて使っていた「山羊の睾丸」が原型となっているそうです。
アメリカやチリなどの新世界の産地では、ブドウの品種やワインのタイプに合わせて、上記の種類の中から選ばれています。
このように、ワインボトルの形状の違いは、生産される地域やワインの種類に紐づいた意味が込められており、ボトルの形状だけで様々な情報を読み取ることができます。ワインボトルの形状の違いもワイン選びのヒントにしてみてください。
ワインボトルの色の意味

形状だけでなく、ワインボトルの色にも重要な意味があります。
色付きのボトルは、遮光性が高く、紫外線や光からワインを守り劣化を防ぎます。最も一般的なのは緑色ですが、茶、緑、青の順に遮光性が高いため、
長期間熟成させるワインには茶色のボトルが使われていることが多いです。
透明のボトルもあります。これはワインの色合いを楽しむためで、ロゼワインやオレンジワイン、スパークリングワインによく使われます。ただし、透明のボトルは紫外線を防げないため、保存場所には注意して早めに飲む必要があります。
ワインボトルの歴史や形状の基本について解説しましたが、ここからは、デザインに焦点を当ててさらに深く掘り下げていきたいと思います。
ワインの容量はなぜ750ml?

ワインボトルの標準的な容量は750mlで、このボトルのことを「ブテイユ(Bouteille)」と呼びます。ブテイユはフランス語でボトルを意味しています。
750mlという容量が標準となった背景には歴史的な経緯があります。かつて、ボルドーワインの最大の輸出先であったイギリスとの貿易では、「ガロン」という単位が使用されていました。1ガロンは約4.5リットル相当で、750mlの瓶を使用するときりの良い1ダース(12本)にすることができます。この換算のしやすさから、標準容量として750mlが広く定着しました。
ところで、日本ワインには720mlの容量の商品も多く見られます。これは、日本でワインの生産が始まった当初、日本酒や焼酎が主流であった時代背景に起因しています。海外基準の750ml瓶を輸入または製造するにはコストがかかるため、当時一般的に使用されていた4合瓶(720ml瓶)をワインにも採用していたのです。現在も明確な決まりはなく、作り手がそれぞれ思い思いの瓶に入れています。720mlの瓶は、日本ワインの独自の文化を反映しているのです。
ワインボトルの瓶底に凹みがある理由は?

瓶底の凹みは「Punts(プント)」と呼ばれます。このデザインには歴史的な経緯や実用的な理由がいくつかあると考えられています。
1つめの理由は「沈殿物を集めるため」です。
最も一般的な説として、ボトル底の凹みは、ワインに発生する澱や酒石といった沈殿物を留め、ワインを注ぐ際に混ざりにくくするためにあるといわれています。これによって、クリアで美しいワインを楽しむことができます。(詳しくは:「ワインの底に溜まっているカスって何?「澱」の正体とおいしく飲む方法」)
2つめの理由は「製造技術による理由」です。
ガラス製造の初期の技術力ではボトルの底を平らにするのは難しかったため、凹みを作ることでガラスの厚さを均一に保ち、安定した形状を確保していたといわれています。この工夫は、技術が発達した現在も伝統的なデザインとして受け継がれています。
3つめの理由は「瓶の強度の向上」です。
ボトルの底に凹みをつけることで全体の強度が増し、圧力に耐えやすくなります。特にスパークリングワインにおいては、そのガス圧に耐えるために重要な役割を果たします。
4つめの理由は「サービス時の実用性」です。
親指を底の凹みにかけ、他の指をボトルの側面に添えることで、ボトルをしっかりと握って支えることができます。さらにこの持ち方には、ワインを注ぐ角度を正確に保ち、ボトルの口からワインが滴り落ちるのを防ぐことができる、動作がスムーズでエレガントに見えるといったメリットもあります。
5つめの理由は「ワイン製造プロセスの効率化」です。
ワインの瓶詰め作業の前段階として瓶を洗浄する際、瓶底が凹んでいることで蒸気の逃げ道ができ、効率的に洗浄を行うことができます。
ワイン瓶底の凹みは、単なる装飾や伝統の継承にとどまらず、ワインの品質や保管において重要な機能を担っています。
例外として、瓶底が平らなシャンパンもあります。ルイ・ロデレール社の「クリスタル」は、18世紀にロシア皇帝に献上する際、底の凹みに危険物が隠せないように、毒物を入れられないようにという理由から、透明で瓶底の平らなボトルで作られました。このデザインは今もトレードマークとして残っています。
ワインの瓶底がギザギザな理由は?
ワインの瓶底のギザギザは「ナーリング」と呼ばれます。ナーリングがある理由は2つです。
1つめは「製造時の利便性のため」です。
瓶はコーティング加工される前は滑りにくく、そのままでは製造ラインでの取り扱いが不便です。凹凸があると平らな底より摩擦が減って瓶が滑りやすくなるため、スムーズに移動させることができ、製造効率が向上します。
2つめは「底部分を割れにくくするため」です。
できたばかりで温かい状態の瓶は、冷たい接地面との温度差で割れやすくなります。ナーリングによって、接地面を面から点にすることで温度差を減らし、割れにくくする工夫がなされているのです。
このように、ナーリングは瓶の製造工程での効率性を高めるために重要なデザインとなっています。
【おすすめ】ワインボトルのラッピング

「日本ワイン店 じゃん」では、ワインボトルのラッピングを承っています。バンダナで包みシックに仕上げるほか、ボトルに寄り添うシンプルなデザインの革リボンは、地元鎌倉の革工房で1つ1つ丁寧に作られており、お好きなメッセージを入れることができます。飲み終わった後は、インテリアやお弁当包みとしてもご活用いただけます!特別な一本に、一味違う彩りを添えてみてはいかがでしょうか。ぜひご検討ください。
→ご注文はこちら
まとめ
今回はワインボトルの形状について、どのように進化してきたのかその歴史と、色や形などデザインに関する疑問を解説していきました。いずれも見た目上だけの理由ではなく、ワインの品質を保証し、その特徴を引き立てるための大切な役割を果たしているのです。
ワインボトルに関する知識を知っていると、ワインの生産地や種類を推測することができ、ワイン選びに役立つことでしょう。普段飲んでいるワインのボトルもぜひこの機会に注目してみてください。
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。