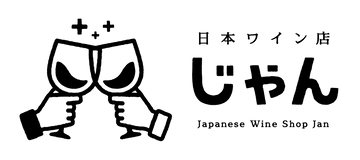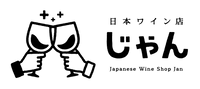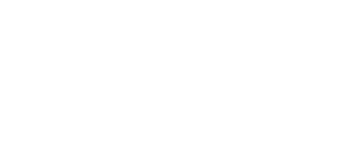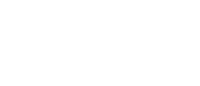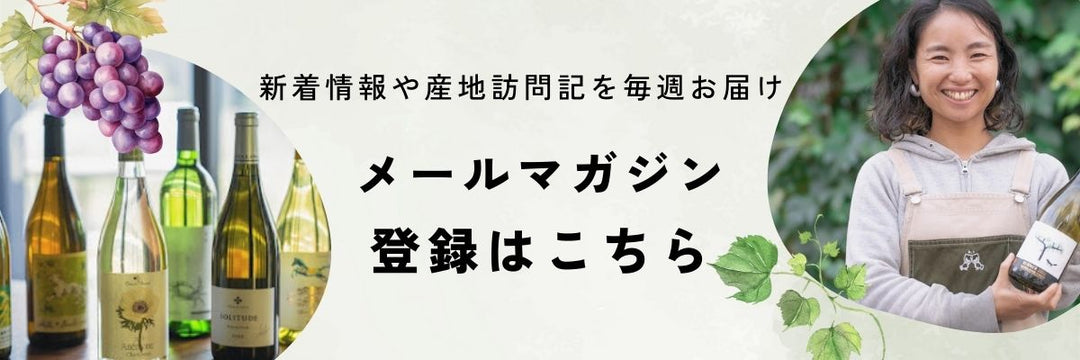「日本ワイン」と「国産ワイン」の違いとは?
日本国内で流通するワインは「日本ワイン」「国産ワイン」「輸入ワイン」の3つに分けられます。国産ワインと日本ワインは、どちらも日本で作られたワインのことを指すのではないの?と疑問に思うかもしれませんが、これらには明確な違いがあります。今回は「日本ワイン」と「国産ワイン」の違いや、日本ワインの特徴について詳しく解説していきます。
目次
「日本ワイン」は国産ブドウのみを使用した、日本国内で製造されたワイン
「日本ワイン」は日本国内で栽培されたブドウのみを原料とし、日本国内で醸造されたワインを指します。輸入された原料を一切使用していない純粋な日本産ワインです。
「国産ワイン」は日本国内で製造されているが、原料は外国産の場合があるワイン
「国産ワイン」は正確には「国内製造ワイン」と定義されますが、海外から輸入されたブドウや濃縮果汁などを原料として、日本国内で製造されたワインです。輸入したワインを国内で加工・瓶詰したものや、ブドウ以外の果実を用いたフルーツワインも国内製造ワインにあたります。
「日本ワイン」表示制度の変遷

これまで日本で作られたワインは「国産ワイン」や「日本ワイン」などさまざまな呼ばれ方をしており、その定義は曖昧でした。この曖昧さを解消し、消費者がより正確な情報をもとにワインを選べるようにするために作られたのが、2015年に国税庁によって制定された「果実酒等の製法品質表示基準」です。この制度では初めて「日本ワイン」の定義が明確にされました。さらにラベル表示も見直され、ブドウの産地や品種、収穫年などの情報をワインのラベルに記載することが義務づけられました。これにより、ワインを選ぶ際に求められる情報がよりわかりやすくなりました。
2018年には「ワイン法」とも呼ばれる果実酒等の製法品質表示基準の改正が行われ、「国内製造ワイン」と「日本ワイン」の違いがより明確化されました。この改正により「国産ワイン」という表現に代わって「国内製造ワイン」という新しい呼び方が導入されました。さらにラベルの表示ルールも一段と厳格化され、消費者が「日本ワイン」と「国内製造ワイン」とを一目で見分けられるよう、表示内容が細かく規定されました。
こうした制度の整備によって、日本ワインとその他ワイン(国内製造ワインや輸入ワイン)との違いが明確化され、 日本ワインの品質を保証し国際市場での競争力を高めるとともに、消費者が安心して選びやすい環境が整いつつあります。
ラベル表示のルール

日本ワインのラベルに産地、品種、ヴィンテージ(収穫年)を表記する際には、EUのワイン法に倣った「85%ルール」が適用されています。このルールを知っておくと、ワインの中身や背景をより深く理解できるようになります。
● 産地名
産地名を記載する場合、その産地で収穫されたブドウが全体の85%以上使用されていて、醸造地も同様である必要があります。
- ・ その地域で収穫されたブドウが85%以上使用されており、収穫地と醸造地が同じ
→「塩尻」などの産地の表記が可能 - ・ その地域で収穫されたブドウが85%以上で、収穫地と醸造地が異なる
→「〇〇収穫」などの表記が可能 - ・ その地域で収穫されたブドウが85%未満の場合
→「〇〇醸造」などの表記が可能
● 品種名
ブドウ品種をラベルの前面に記載する場合、その品種が全体の85%以上使用されている必要があります。
- ・ 単一品種を85%以上使用
→「甲州」などの品種表記が可能 - ・ 2つ以上の品種で85%以上使用
→ 割合を併記して多い順に表記可能
● ヴィンテージ(収穫年)
特定の収穫年を記載する場合、その年に収穫されたブドウが全体の85%以上使用されている必要があります。
日本ワインの特徴

日本ワインは爽やかな果実味と繊細な味わいが特徴です。 これは、日本固有のブドウ品種である甲州やマスカット・ベーリーAの特性で、甲州は軽やかな酸味とフレッシュさ、マスカット・ベーリーAはフルーティーな香りと柔らかいタンニンによって、日本ワインの独自の味わいを形成しています。日本固有品種としては、他にもブラッククイーンやヤマソーヴィニヨンといった品種も注目されています。
これらの固有品種に加えて、それぞれの地域に適した外来品種も活躍しています。例えば、長野県ではシャルドネが高品質な白ワインを生み出し、北海道ではピノ・ノワールが繊細でエレガントな赤ワインとして評価されています。これらの外来品種は、日本の気候や土壌の特性に適応しながら、日本ワインならではの風味を生み出すのに一役買っています。
当店では日本ワインを専門に扱っています。日本の気候風土で育ったブドウから作られる日本ワインの良さは、何と言っても日本の食事によく合い、スイスイ飲める美味しさであること。お寿司やお鍋、刺身や煮物など、普段の食事に寄り添う美味しさを体感してみてください。
● グレイス甲州
2023年5月に開催されたG7広島サミットの夕食会では、日本への理解をより深めてもらうことを意義の一つとして掲げ、全国各地の食材を使った和洋折衷の料理とともに、日本のお酒が各国の首脳に振る舞われました。その席で提供されたワインのひとつが「グレイス甲州」です。「グレイス甲州」は、山梨県の老舗ワイナリー・中央葡萄酒が手がける辛口の白ワインで、柑橘系の香りとほのかな苦みが特徴です。甲州種の個性を丁寧に引き出した1本で、国内外のワインコンクールでも数々の受賞歴を誇ります。日本ワインに興味がある方は、まずはこの一本から試してみるのもおすすめです。

柑橘系の香りとほのかな苦みが心地よく、甲州らしさを素直に感じられる辛口の白ワイン
● NselecT ヤマソーヴィニヨン
石川県能登地域で栽培された、日本固有の品種であるヤマソーヴィニヨン種を使用した赤ワインです。能登ワインではこの品種の栽培に力を入れており、近年の日本ワインコンクールでもその品質が高く評価されています。山ブドウ由来の野性的な香りと、日本の原風景を思わせる素朴な風合い、そしてしっかりとした骨格ある味わいが特徴。牛肉とアスパラガスの炒め物など、旨味とコクのある料理とのペアリングがおすすめです。

日本固有品種「ヤマソーヴィニヨン」を使った赤ワイン。野性的な香りと骨格ある味わい
日本ワインの代表的な産地

実は日本ワインは、北は北海道から南は鹿児島まで国内のほとんどの地域で造られています。また、日本のワイナリー数は2024年1月時点で493場で、前年比25場増加と増えてきています。
日本ワインの生産量、ワイナリーの数は、ともに1位が山梨県で、2位長野県、3位北海道と続きます。全国にあるワイナリーのうち、半数近い実に48.4%がこの上位3県に集中しており、生産される日本ワインの69.5%はこれらの地域で造られています。ちなみに、47都道府県の中で唯一、佐賀県にはワイナリーがありません。(2025年3月現在)
山梨県は古くからブドウ栽培とワインの醸造が行われている地域の一つであり、ワイン産業の中心地として知られています。その評価を裏付けるように、2013年には国税庁による「GI(Geographical Indication)」地理的表示制度に基づいて、日本で初めてGIに認定された地域となりました。
GI制度とは?
GI(地理的表示)制度とは、その地域ならではの特徴や品質を持つ農産物や酒類を保護するための仕組みです。GIマークが付与される商品には、「その土地で生産された原材料を使用し、地域の特性がしっかりと反映されていること」、そして「地域に根ざした製法や伝統的な技術を用いて生産されていること」といった条件が求められます。
ワイン文化が深く根付いているヨーロッパでは、原料となるブドウの栽培された土地の気候や土壌の特性がワインの香りや味わいに大きく影響すると考えられており、こうした地理的表示制度は、品質の保護だけでなく産地ごとの個性を際立たせ、ブランド価値を高めるために重要な役割を果たしています。この制度は世界各国で導入されており、例えばフランスでは「シャンパーニュ」「ボルドー」「ブルゴーニュ」といった地名が、その土地で厳格なルールに基づいて造られたワインにのみ使用できるよう法律で保護されています。
日本の気候とワイン造り

世界的に有名なブドウの産地は、一般的に降水量が少なく日照時間が長いことに加え、年間を通して一日の気温差が大きいという特徴があります。これらの条件は、ブドウの成熟や糖度、酸のバランスにとって理想的とされています。一方で、日本は降水量が多く一日の気温差が小さい地域が多いため、かつてはワイン用ブドウの栽培にはあまり適していないとされてきました。しかし近年では、日本の気候に適したブドウ品種の開発や、栽培・醸造技術の向上が進んだことで、国内各地で質の高いワインが生産されるようになり、国際的な評価を得る日本ワインが増えてきました。
また南北に長い日本列島では地域によって気候特性が異なるため、日本ワインは土地ごとの多様性を楽しみやすいという魅力もあります。
日本国内では、ブドウ酒(ワイン)の区分でGI認定を受けている地域は、山梨県をはじめ、北海道、山形県、長野県、大阪府の5地域に限られています。それぞれの土地が持つ気候や風土、醸造の伝統が評価され、地域ブランドとしての価値が守られています。
日本ワインの産地別傾向と代表品種

日本ワインの生産量上位3地域を比較してみるとそれぞれ異なる特徴がみられます。山梨県と北海道では白ワインの製成割合が高く、一方で長野県は赤ワインの製成割合が多い傾向にあります。このような傾向は、各地域の気候や土壌、栽培されている品種の違いが、ワインの色やスタイルに表れていると考えられます。
国内で最も多く生産されているブドウ品種を見てみると、赤ワイン用はマスカット・ベーリーA、白ワイン用は甲州がトップ。白ワイン用品種が全体の45.1%、赤ワイン用品種が42.0%を占めており、白ワイン用品種の生産量がわずかに上回っていることがわかります。品種別に見ると、白ワイン用品種の上位は1位が甲州(15.3%)、2位がナイアガラ(11.4%)、3位がシャルドネ(6.5%)。赤ワイン用品種では、1位がマスカット・ベーリーA(13.6%)、2位がコンコード(8.3%)、3位にメルロー(6.5%)が続いています。
こうした品種の構成や地域ごとの傾向を知ると、日本ワインの個性や味わいの背景をより深く理解することができます。ワイン選びの参考や、旅先でワイナリーを訪れる楽しみも広がるでしょう。
まとめ
2018年のデータによると、国内で製造されたワインのうち日本ワインは20%程度。また、日本国内で流通するワインの約70%は海外から輸入されたワインが占めており、日本ワインは市場の中ではまだまだ少数派というのが現状です。このように、国内のワイン産業は着実に発展しつつあるものの、流通量の面ではまだ成長途上にありますが、日本ワインを選ぶことは生産者への応援や地域の取り組みを支えることにもつながります。食卓や贈り物の選択肢に日本ワインも加えてみてください。
また、つくり手との距離が近いことも日本ワインの魅力のひとつ。産地の気候風土を想像しやすく、行こうと思えば行ける距離にワイナリーがあると楽しみ方も広がります。当店では、全ての取扱いワイナリーに足を運び、実際に見て聞いてワインを仕入れています。つくり手の情熱や想いもぜひ一緒に楽しんで下さい! ▶ つくり手紹介の記事はこちらから
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。