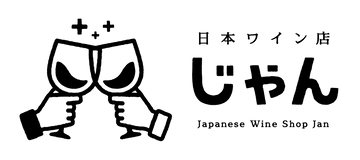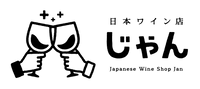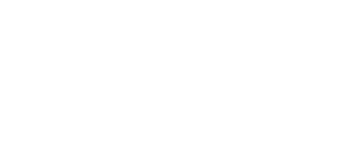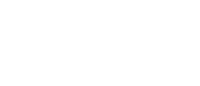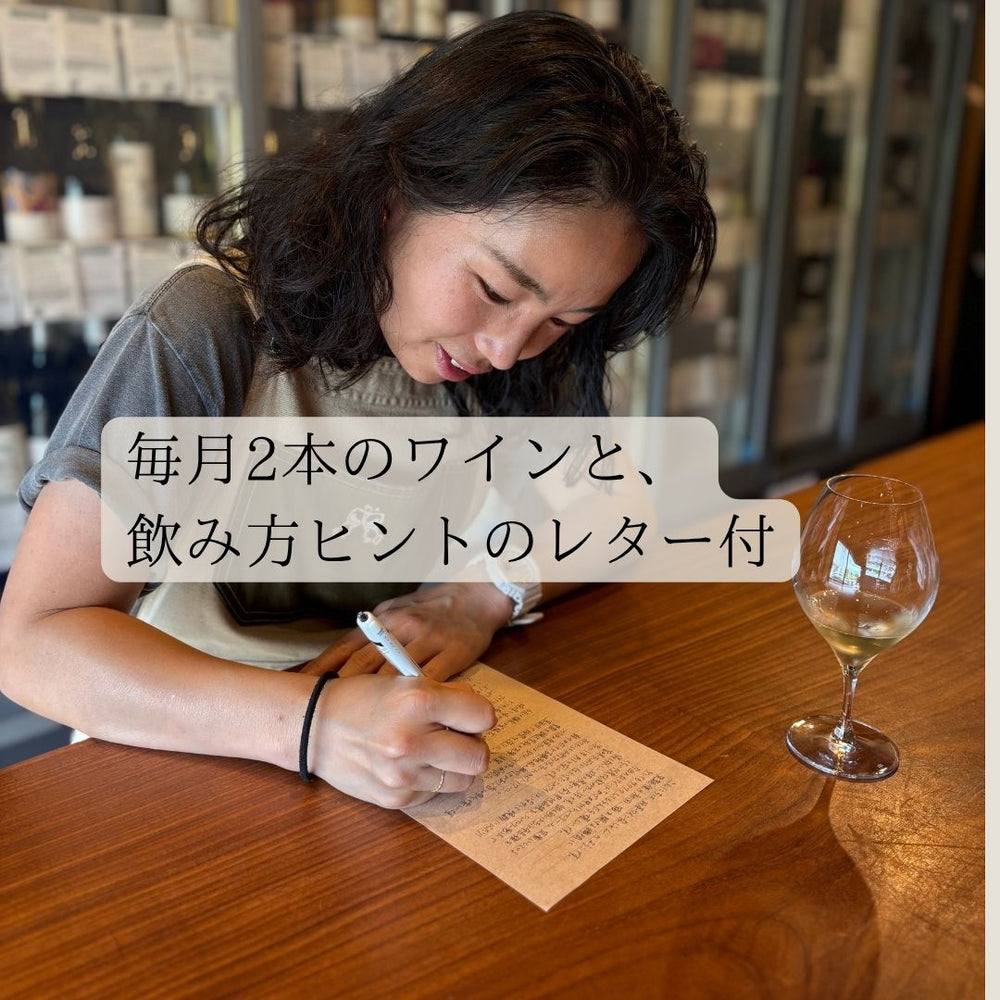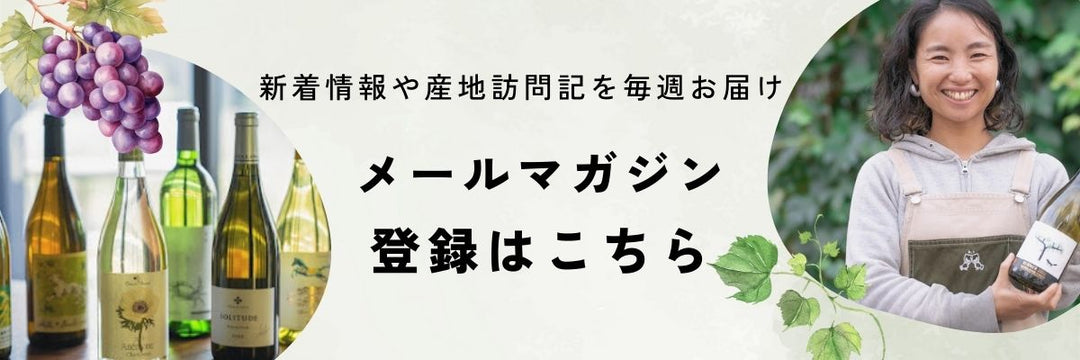「GI山梨」や「GI長野」ってどういう意味?日本ワインの原産地呼称制度について解説
ワインのラベルをじっくり見たことはありますか? 産地やブドウの品種、醸造方法など、実はたくさんの情報が詰まっているんです。その中でも、「原産地呼称制度」は、ワインのルーツや品質を知るための大切なヒントになります。今回は原産地呼称制度とは何なのか?ヨーロッパと日本の制度の比較や日本の認定産地について解説します。
目次
ワインの原産地呼称制度とは?

ワインの原産地呼称制度といえば、代表的なのがフランスのAOP(Appellation d'Origine Protégée = アペラシオン・ドリジーヌ・プロテジェ)です。これは「その土地で栽培されたブドウを使い、その地域で決められた作り方で作っている」ことを保証する制度で、品質の信頼性を高めブランド価値を付加すると同時に、その地域ならではの個性を守る役割も持っています。
AOPの「d’Origine」の部分はそのワインが生産された地域名に置き換えられてラベルに表記されます。例えばブルゴーニュ地方で造られたワインであれば、「Appellation Bourgogne Protégée」や「AOP Bourgogne」という表記をされます。ボルドーやシャンパーニュといった世界的に知られるワイン産地はこのAOP制度のもとで管理されており、ラベルを見るだけでワインの出自や品質についての情報を得ることができるのです。
AOPとAOCの違い
AOPはもともと、AOC(Appellation d'Origine Contrôlée = アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ)という名称で、1930年代から続くフランス独自の品質保証システムでした。2009年にヨーロッパの規定に合わせて名称がAOPへと統一されましたが、本質は変わっていません。AOCはフランス国内では現在でもよく使われており、ラベルにも表示されていることがあります。AOPやAOCはフランスの食文化を守るための大切な仕組みであり、ワインだけでなく、チーズやバター、オリーブオイルなどのさまざまな食品にも適用されています。
ヨーロッパの原産地呼称制度、PDOとPGI

原産地呼称制度は、ワインの品質や個性を守るための仕組みとして、フランスだけでなく世界各国でそれぞれの形で整備されています。なかでもヨーロッパは、多くの国が地続きで文化や食の交流が盛んであるため、国ごとの制度だけではなく共通の基準が必要とされてきました。そこで導入されたのが、「PDO(Protected Designation of Origin/保護原産地呼称)」と「PGI(Protected Geographical Indication/保護地理的表示)」という2つの制度です。
PDOは、ブドウの栽培からワインの醸造・瓶詰めに至るまですべての工程が特定の地域内で行われていることが条件とされ、その土地の風土や伝統が色濃く反映されたワインに付与されます。一方、PGIは工程や原材料において地域と一定の関わりが認められればよく、すべての工程がその土地で行われていなくても認証の対象となる、より柔軟な制度です。
国ごとに異なる原産地呼称制度

EU加盟国ではPDOやPGIのような共通の枠組みを採用しつつも、各国が自国の歴史や文化に根ざした独自の呼称制度を併用しています。たとえばイタリアでは、PDOに対応するものとして「DOC(Denominazione di Origine Controllata)」や、より厳格な「DOCG(Denominazione di Origine Controllata e Garantita)」という制度が存在し、伝統的な製法に基づいた高品質なワインに付けられます。一方、PGIに相当する「IGT(Indicazione Geografica Tipica)」は、産地の特性を活かしながらも自由度の高いスタイルのワインに使われています。
このように呼称や運用の細かなルールは国ごとに異なりますが、「特産品としての価値を保証する」という目的は共通しています。また、ヨーロッパの共通ルールの下で整合性が図られていることは、消費者にとって理解しやすく、産地や品質の信頼性を判断する手がかりとなります。さらに、これらの制度には各国が育んできたワイン文化の価値観や哲学が反映されており、単なる認証表示を超えて、その国が誇る品質基準を満たしている証として重要な意義を持っています。
日本の原産地呼称制度「GI(地理的表示)制度」

こうしたヨーロッパの制度と同様に、日本でもワインの産地の個性や品質を守るための仕組みが整備されています。それが「GI(Geographical Indication/地理的表示)制度」です。この制度は、その土地ならではの特性を持つ農林水産物や食品を「地域ブランド」として国が認める制度で、ワイン(ぶどう酒)もその対象のひとつです。
ワインについては、ブドウの産地やワインの製造方法などについて国が定めた規定を満たすと、GIの表示が認められます。この制度は、ヨーロッパの原産地呼称制度であるPDOやPGIと連携する形で設計されており、日本ワインを世界に向けて発信するための重要な基盤になっています。
なお、ヨーロッパのPDO・PGI制度は主にワインや食品に適用され、原料の栽培から製造まですべての工程が指定地域内で行われることが原則ですが、日本のGI制度はより柔軟な運用がされており、農林水産物や食品全体を対象とする点で独自の特徴を持っています。
GI制度の目的と背景

日本のGI制度は、特定の地域で生産される農産物や酒類などの品質や特性を保護し消費者にその由来を正しく伝えること、そして地域経済の支援を目的として整備されました。その背景には、地域ブランドとして長年親しまれてきた食品や酒類が、模倣品や不正表示によって本来の価値を損なわれてしまうという課題がありました。
当初は日本酒などが中心でしたが、2015年からはワインや焼酎も対象に加わり、日本ワインの品質を証明するための重要な制度として活用されるようになりました。日本酒では「山田錦」や「出羽桜」、焼酎では「鹿児島焼酎」などがGIに認定されています。
GI制度は現在、酒類に関しては国税庁によって運用されており(農産物や食品は農林水産省が管轄)、厳格な基準に基づいて審査・認定が行われています。GI制度は日本の食や酒の文化的・地域的な価値を守り、次世代へと受け継いでいくための大切な制度といえるでしょう。
GI制度のメリットと課題
GI認証マークは、どこで・どのように造られたのかが明確に示されている証しです。特定の地域で育てられたブドウを用い、地域の風土や伝統的な技術に根ざして造られていることが保証されています。消費者にとっては信頼して選べる目印となるほか、模倣品や不正表示から本物の価値を守るための仕組みにもなっています。
また、GI制度を通じて消費者が地域産品を手に取る機会が増えることは、その土地の農業やものづくりを支えることにもつながります。信頼性と個性が保証されることで地域ブランドとしての価値が高まり、他の産地との差別化も図れるようになります。
一方で、GIの存在や意味が消費者に十分認知されていない、認定のための手続きや審査が煩雑といった課題もまだまだあります。
日本ワインは山梨や長野などの5産地がGIに認定

日本ワインは現在、山梨、北海道、山形、長野、大阪の5つの産地がGIに認定されています。GIに認定されている地域が5つに限られているのには、いくつかの理由があります。認定を受けている地域はワイン造りの歴史が比較的長く、品質や地域ごとの特性が確立されていることが特徴です。さらに、ワイン用の栽培に適した環境を備えていることも、重要な要素となっています。
これらの地域で認められたワインには、GI認証マークが付けられており、「品質と地域性が保証されたワイン」であることの証になっています。ただし、認定地域で造られているワインすべてにGIマークが付けられるわけではありません。認証マークをつけるには、各地域ごとに定められたアルコール度数、使用する品種、糖度などの厳しい生産基準をクリアする必要があります。
● GI山梨
・指定日:2013年7月
・アルコール度数:8.5%~20.0%
・品種:甲州、マスカット・ベーリーA、カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネなど42品種
・果汁糖度:甲州14.0%以上、ヴィニフェラ種18.0%以上、その他16.0%以上
・特徴:ブドウ本来の香りや味わいが楽しめる、穏やかな酸味
● GI北海道
・指定日:2018年6月
・アルコール度数:14.5%以下
・品種:ピノ・ノワール、シャルドネ、ケルナー、ツヴァイゲルトなど57品種
・果汁糖度:ヴィニフェラ種16.0%以上、ラブラスカ種13.0%以上、ヤマブドウ種及びハイブリッド種15.0%以上
・特徴:果実の豊かな香りと酸味・甘味の調和がとれた味わい
● GI山形
・指定日:2021年6月
・アルコール度数:7.0%~20.0%
・品種:シャルドネ、メルロ、デラウェア、ナイアガラなど51品種
・果汁糖度:ヴィニフェラ種16.0%以上、ラブラスカ種12.0%以上、その他14.0%以上
・特徴:本来の味や香りが引き立った爽やかな酸が特徴
● GI長野
・指定日:2021年6月
・アルコール度数:7.5%~20.0%
・品種:メルロ、シャルドネ、ソーヴィニョン・ブラン、コンコードなど50品種
・果汁糖度:ヴィニフェラ種 17.0%以上、ラブラスカ種(A類)17.0%以上、日本系交配品種(A類)17.0%以上
・特徴:品種ごとの本質的な香味の特性がはっきりと表れる
● GI大阪
・指定日:2021年6月
・アルコール度数:9.0%以上
・品種:デラウェア、甲州、マスカット・ベーリーAなど36品種
・果汁糖度:デラウェア18.0%以上、甲州14.0%以上、その他12.0%以上
・特徴:凝縮された果実味と穏やかな酸味、心地よい余韻
GI認定ワインは、各地域の酒造組合のホームページなどでも確認することができます。また、各地でワインフェスや試飲イベントなどが開催されており、実際に味わいながらその地域の魅力に触れることができます。ぜひ現地を訪れて日本ワインの奥深さを体験してみてください!
GIに認定されるためには

GIに認定されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。まず、申請は個人ではなく生産者団体が行うことが求められます。また、「①そのワインが特定の地域で生産されていること、そしてその地域の気候や風土が品質に影響を与えていること」が重要です。さらに、「②地域に根ざした伝統的な製法や、独自の品質的な特徴を持っていること」、「③市場での社会的評価(認知度や信頼性)が確立されていること」、「④名称が地理的表示として適切であること」も条件となっています。これらの条件を満たした上で、国税庁による審査を経て正式に認定されます。
今後も新たに認定される地域が増えていくかもしれません。
まとめ
原産地呼称制度は品質や信頼性を保証する上で有効な仕組みですが、それがすべてではありません。制度に則らないワインの中にも、個性的ですばらしいワインはたくさんあります。大切なのは制度を理解したうえで、選択肢を広げていくこと。ワインを選ぶときの「ヒント」として制度を活用しながら柔軟な目線を持つことが、ワインの楽しみ方をより豊かにしてくれます。
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。