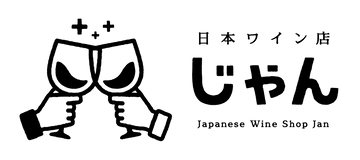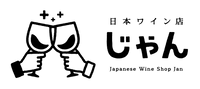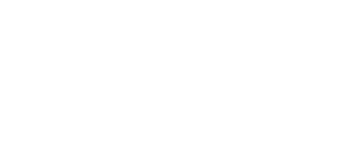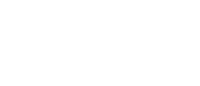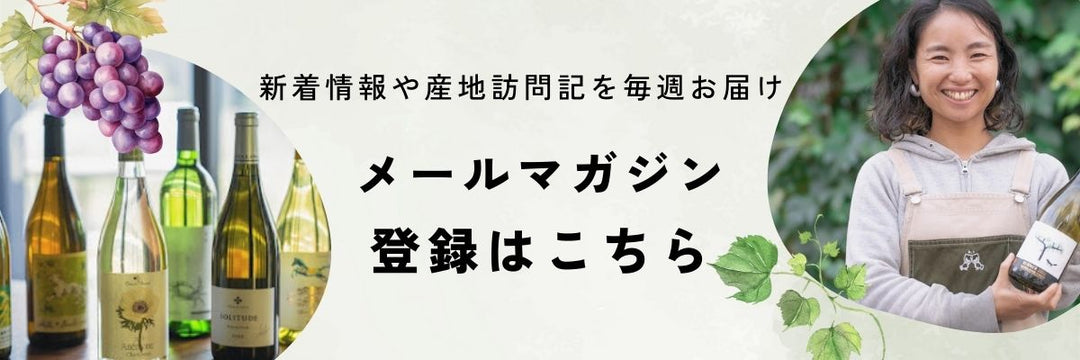赤ワインの「ボディ」とは?その基準や違いを解説
フルボディとか、重いとか、ワインを表現するときによく聞く言葉ですよね。でもそれって具体的にどういう意味か?その疑問に詳しく解説をします。そして、日本ワインの中でもボディのしっかりしたワインをいくつかご紹介します。
目次
赤ワインのボディは大きく分けて3つのタイプがある
赤ワインの「ボディ」とは、ワインの口当たりや質感を表す言葉です。 ワインのボディは一般的にライトボディ(軽い)からフルボディ(重い)までに分かれ、そのボディ感はワインの濃度と口当たりに関連しています。
1. ライトボディ
ライトボディの赤ワインは軽やかで透明感があり、口当たりが軽いです。 通常、アルコール度数が低く、果実味や酸味が前面に出ています。 ブドウ品種ではピノ・ノワールやガメイなどが典型的なライトボディの赤ワインです。
2. ミディアムボディ
ミディアムボディの赤ワインとは、ライトボディとフルボディの中間程度のワインを指します。バランスが良く、豊かな果実味や複雑な味わいを持つことがあります。ブドウ品種ではルローなどが主に該当します。
3. フルボディ
フルボディの赤ワインは濃厚で力強く、口に含むと強く味覚を刺激し、余韻が長く広がります。 高いアルコール度数と濃密なタンニンが特徴で、熟成によって複雑さが増します。 カベルネ・ソーヴィニョンやシラーなどが代表的なフルボディの赤ワインです。
赤ワインのボディに影響を考える要素は何か?
赤ワインのボディに影響を考慮する要素として、上記に書いたブドウ品種意外には、こんな要素もあります。
〇収穫時期
どのタイミングで収穫するかは、つくりたいワインによってつくり手が選択します。
一般的には、収穫時期を遅らせることでブドウの糖度・熟度が増し、よりフルボディのワインを作ることが可能となります。
〇 アルコール度数
ワインのアルコール度数はボディに影響を与えます。 高いアルコール度数はフルボディ、低いアルコール度数はライトボディのワインとなります。 アルコール度数はどうやって決まるのかについては、こちらのブログで詳しく解説しています。
〇タンニン
赤ワインに含まれる成分「タンニン」は、口当たりやボディ感に影響します。 タンニンが多いとワインをフルボディにし、タンニンが少ないとライトボディに仕上がります。 ブドウの皮や種子からの抽出がタンニンとなります。
白ワインにも「ボディ」はあるの?
白ワインにも「ボディ」という概念があります。 ボディは赤ワインに関連して語られることが多いですが、他のタイプのワインにも適用されます。
一般的にはライトボディの白ワインは、すっきりとした口当たりで高い酸味が特徴のブドウ品種、ピノ・グリやソーヴィニョン・ブランなどが該当します。 フルボディの
白ワインは、濃密でクリーミーな口当たりで、樽で熟成されたり、マロラクティック発酵を経て作られることがあります。ブドウ品種の例としては、シャルドネやヴィオニエなどがあります。
比較的「重たい」ボディの日本ワイン3選
気候風土で栽培されたブドウを使った日本ワインは「うす旨」や「出汁感がある」と表現されるものも多く、海外ワインのフルボディ程の「重たい」ワインは少ないといえるでしょう。ただ、繊細な日本ワインだからこそ、お寿司やお刺身、素材の味を活かした繊細な和食の料理を引き立てることができる、そこが日本ワインの良さでもあります。
そんな日本ワインの中でも、比較的「重い」ボディの日本ワインはこちら👇
アメリカンオークでの熟成により、しっかりしたボディと華やかな香りが楽しめる赤ワインです。 シャトーメルシャン勝沼ワイナリー醸造長を目指した味村興成さんが立ち上げた、メルロー品種に特化したワイナリー。
当店(日本ワイン酒場じゃん)で提供時、人気が大爆発した赤ワイン。 日本のワインは軽くてちょっと…と思う方もこれを飲めば見方が変わるはず! とても果実味が豊かでしっかり飲みごたえのある赤ワインです。

アメリカンオークで樽熟成させた甲州品種酒の白ワイン。黄金色に輝くとろみのあるワインで、甲州のもつ切れ味と樽熟成からくる濃厚さの良いところ取り。当店(日本ワイン酒場じゃん)の角打ちでも非常に人気で、飲んだ方はかなりの確率でボトルを購入されます。