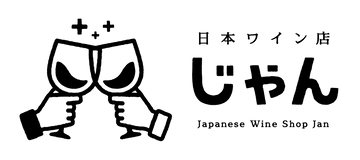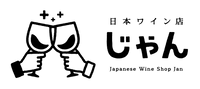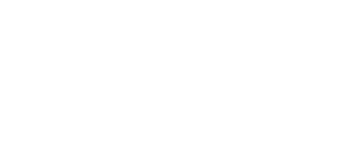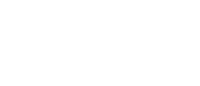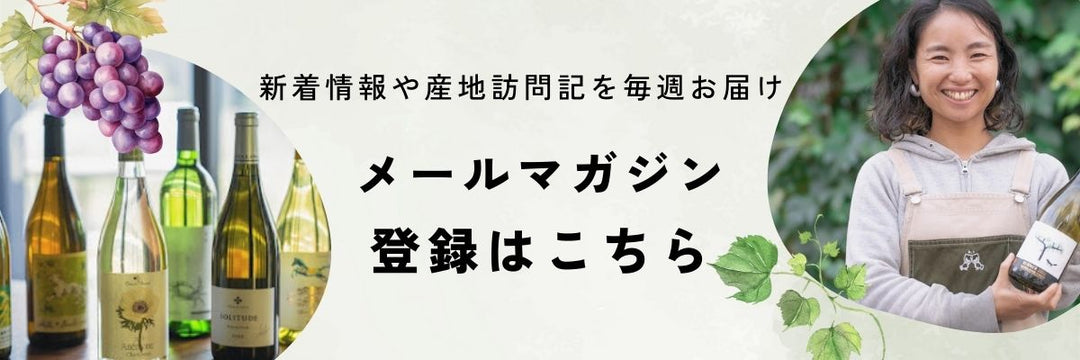杉の香に迎えられる吉野の蔵
新緑がしっとりと山を覆い、川のせせらぎが響く吉野川のほとりに美吉野醸造はあります。訪れたのは初夏。山々に囲まれた長い道のりを抜けると、目の前に広がるのは大きな清流。川沿いを進んでいくと、石垣に囲まれた立派な日本家屋が見えてきます。
事務所に一歩足を踏み入れると、杉のすがすがしい香りがやさしく迎え入れてくれ、思わず深呼吸。蔵は改装中でしたが、静謐な空気に満ちていて、自然と気持ちが引き締まります。


歴史と自然が息づく、吉野という土地の力
杜氏であり専務の橋本さんは、お会いしてすぐ、吉野の歴史や地域性について熱心に教えてくださいました。蔵のある吉野川の南側は、古くから修験道の文化が息づく地。その名残か、今も静けさとともにどこか神聖さを感じさせる空気が流れているように感じます。
もう一つ、吉野を語るうえで欠かせないのが「吉野杉」です。江戸時代、この地で育まれた杉材は、酒樽や酒造用の大桶に加工され、香り豊かな樽酒として人々に親しまれてきました。その伝統は今も息づいており、
美吉野醸造では吉野杉で造られた麹室や木桶が現役で活躍しています。
代表銘柄「花巴」や「百年杉 木桶仕込み」も、吉野杉の樽を使って仕込まれた逸品。この地ならではの唯一無二のつくりです。
地域と共に歩む、米と向き合う酒造り
美吉野醸造の酒づくりは、地域の米づくりと深く結びついています。使われている米はすべて、地元の農家さんが丹精込めて育てたもの。生産者ごとに品種や精米歩合まで把握し、また全量を買い上げることで地域の農業を支えながら、米に向き合った酒造りを行っています。
麹や酒母も同じく、米の旨味をいかに引き出すかが考えられたものです。酒母は、速醸・山廃・水酛といった異なる酒母を複数使い分けることで酸の引き出し方に幅を持たせており、米の旨みをしっかりと感じながら、際立つ酸が伸びやかに広がる味わいです。
「個性はつくるものではなくにじみ出てくるもの」という橋本さんの言葉や、「地元農家の方が土地の力を活かして作った米への思いを汲み、その生産方法に合わせた酒造りをする」という美吉野醸造の酒づくりからは、土地の恵み、そして地元の産業に関わる人々への深い敬意を感じます。

吉野の風土に寄り添う、美吉野醸造の酒づくりの美学
酵母の選び方にも自然との向き合い方が表れています。
酵母は「濃糖圧迫」という方法で、あえてストレスのかかる環境をつくり、その中で生き残ったものだけを酒づくりに使います。この考え方は吉野の林業にも重なるところがあるそうです。吉野杉は、あえて密に植えて日光の届きにくい環境をつくり、ゆっくりと成長させます。間伐などの手入れを行いながら、長い年月をかけ競い合うようにまっすぐに伸びた杉は、年輪が詰まり、樽や桶にしても漏れにくい良材に育ちます。人がつくり込むのではなく自然に委ね、その厳しい環境を生き残ったものは良いものに育つ。酒の味も同じ、という話はとても興味深かったです。
橋本さんは、蔵の姿勢を「不自由の中の自由」という言葉で表現されていました。今はお米も酵母も全国から選べる時代。温度や湿度といった環境も細やかに調整できるようになっています。そのようにあらゆる選択肢がある中で、美吉野醸造はあえて「吉野の風土に寄り添う」ことにこだわり、その制約の中で最大限の表現を追求しています。そこには、この土地にある意味を重んじ歴史や風土への誇りを酒に映す、美吉野醸造の美学を感じました。