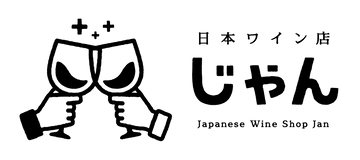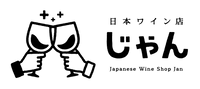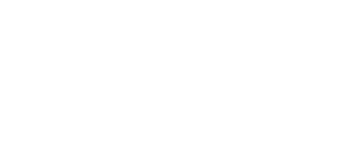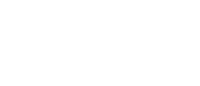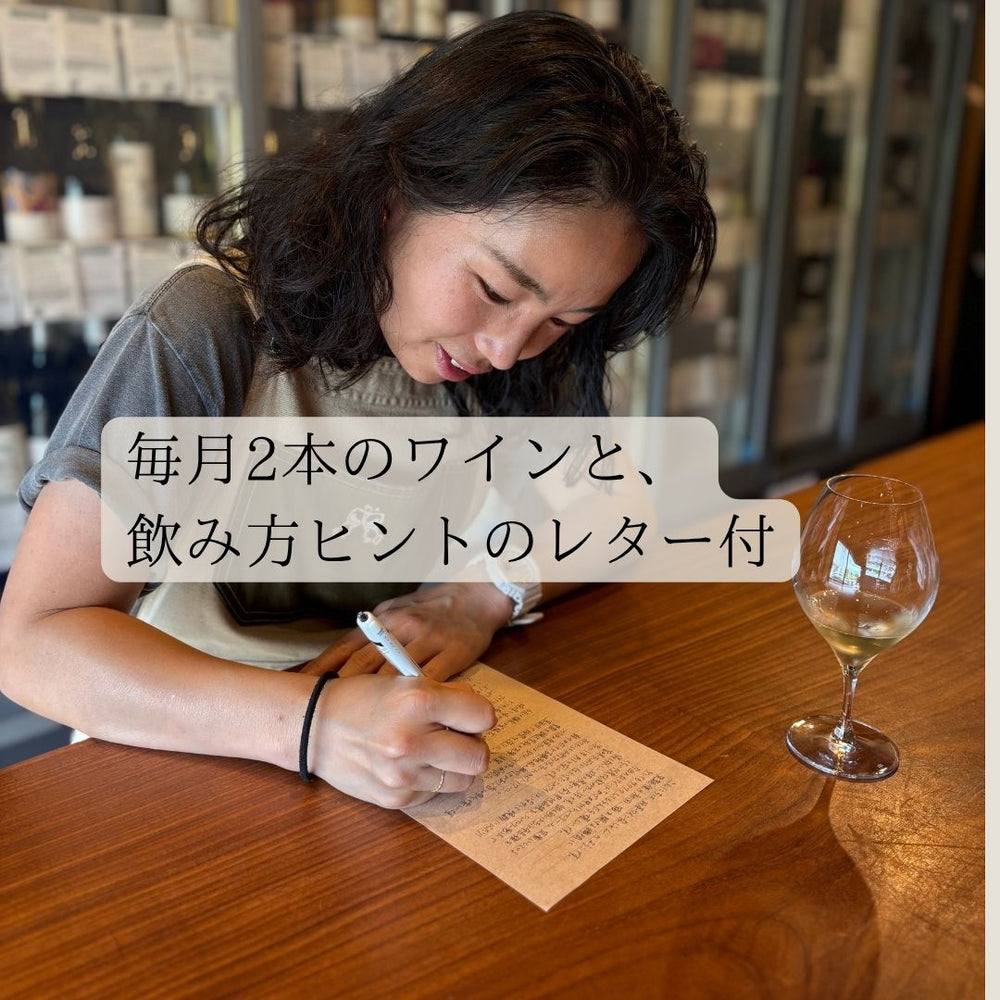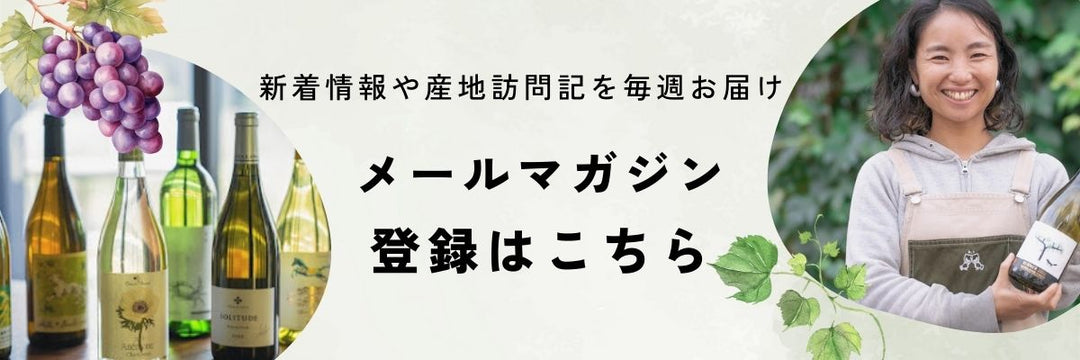ワインのアルコール度数って、どうやって決まるの?
ワインを飲むときに気になることの1つ、アルコール度数。飲む量の目安としてはもちろん、料理との相性の参考にしたり、ワインの楽しみ方そのものにも影響する要素です。この記事では、ワインのアルコール度数はどのように決まるのか?そして、ワインの種類によって度数にどのような違いがあるのか?他のアルコール飲料との比較など、ワインのアルコール度数にまつわるさまざまな疑問について解説していきます。
目次
ワインのアルコール度数はどのくらい?

ワインのアルコール度数は、厚生労働省の定義によると12%とされています。ただし、種類やスタイルによって異なり、一般的には11%〜15%の範囲のものが多く流通しています。
アルコール度数とは、飲料全体の体積に対するアルコールの割合を示すもので、「アルコール度数計(酒精計)」によって測定されます。測定時の温度も決まっており、日本では15℃が基準とされています。これは、温度によって液体の密度が変化し、測定値に影響を及ぼすため、正確な測定には一定の温度条件が必要だからです。
日本では、酒税法や食品表示法といった法律により、アルコール度数の表示が義務づけられています。気になる方は、購入時にラベルを確認する習慣をつけると安心です。
他のアルコール飲料の度数と比較

アルコール度数を比較してみると、低い順に、ビールが4〜6%、ワインが11〜15%、日本酒が13〜16%、焼酎が25〜35%、そしてウォッカやウイスキーなどは40%以上となっています。ワインはビールに次いでアルコール度数が低く、適度なアルコール感がありつつ料理の味を邪魔しないため、食事と一緒に楽しみやすく、ソーシャルな場にもよく合います。ちなみに、ビールやワイン、日本酒は「醸造酒」に分類されますが、焼酎やウイスキーなどの「蒸留酒」は、発酵後に蒸留という工程を経てアルコール度数を高めているため、自然と度数が高くなります。
私はお酒があまり強い方ではないのですが、食事と一緒にお酒を楽しみたい派。以前は日本酒をよく飲んでいましたが、日本酒だと酔いが回りやすく、食事中ずっと飲み続けるのは難しかったです。そんな時に出会ったのが日本ワイン。日本の食事とよく合う繊細な味わいとちょうどよいアルコール感が心地よく、自分のニーズにピッタリ合ったのです。同じような悩みを持っている方には、ぜひ一度ワインを試してみてほしいと思います。
アルコールはどのくらいで抜ける?

アルコールの身体への影響や酔いの程度は、「摂取したアルコールの総量」に左右されます。そのため、適量を心がけるには、アルコール度数だけでなく、どれだけの純アルコールを摂取しているかを意識することが大切です。たとえば、ワイン1杯(120ml)あたりに含まれる純アルコール量は約12gとされています。
(※飲酒量 [単位:ml] × アルコール度数 [ワインの平均度数12~13%] ÷ 100 × 0.8 [アルコールの比重] で計算)
体内でアルコールが分解される速度には個人差がありますが、一般的な目安としては「体重×0.1gのアルコールを1時間で分解できる」とされています。つまり、体重60kgの人であれば、1時間におよそ6gのアルコールを分解できるという計算になります。ただし、これはあくまで目安であり、性別や年齢、遺伝的要因、飲酒習慣などによって異なる場合があります。
また同じ量でも、アルコール度数が高い飲料は純アルコール量も多いため、血中アルコール濃度が上がりやすくなり分解にも時間がかかります。「どれくらい飲んだか」だけでなく、「何を/どのくらいのアルコール度数で飲んだか」にも目を向けて、自分の体調や状況に応じて判断するのが大事です。
ワインのアルコール度数はどう決まる?

ワインを造る過程には「アルコール発酵」と呼ばれる工程があります。この工程では、ブドウ果汁を発酵タンクに移し、そこに酵母を加えます。酵母は、ブドウ果汁に含まれる糖分を分解し、アルコールと二酸化炭素を生成します。このはたらきによって、ワインのアルコール度数は決まります。
一般的に、原料となるブドウに含まれる糖分が多い(甘いブドウ)ほど酵母のはたらきは活発になり、生成されるアルコールの量も多くなるため、最終的なアルコール度数は高くなります。
ワインのアルコール度数に影響する、ブドウの糖度はどう決まる?

ワインのアルコール度数に大きく影響する要因のひとつが、原料となるブドウの「糖度」です。これは、主に「ブドウの品種」「産地の気候」「収穫時期」によって決まります。
● ブドウの品種
ワイン用ブドウは世界に約800種あるとされており、その品種によって糖度の高さには違いがあります。シラーやスペインのグルナッシュ、カリフォルニアのジンファンデルといった品種は糖度が高くなりやすく、これらから造られるワインはアルコール度数が15%を超えることもあります。
● 産地の気候
ブドウがしっかりと熟して糖度が高くなるには、気候も大きな役割を果たします。平均気温が10〜20℃と温暖で、日照時間が長い、昼夜の寒暖差が少ない、降水量が少ない環境が、ブドウ栽培には適しているとされています。これらの条件を満たす代表的なワイン産地としては、フランスのボルドー、スペインのリオハ、カリフォルニアのナパ・ヴァレーなどが知られています。
日本では、日照時間が長く寒暖差が少ない山梨県のワインは果実味豊かで力強い味わいに、冷涼な気候の北海道や長野のワインは酸がきれいで繊細かつエレガントな味わいになる傾向があります。(詳しくは:今、注目の長野ワイン!千曲川ワインバレーの特徴を徹底解説 )
● 収穫時期
同じ品種のブドウでも、収穫時期が遅くなるほど糖度は高くなる傾向があります。これはブドウが樹上で長く成熟することにより、光合成による糖の蓄積や乾燥による水分減少によって糖分が凝縮されるためです。収穫後のブドウを干しても、同じような効果が得られます。通常より遅く収穫することで甘さを強調した「遅摘みワイン(レイトハーベスト)」というワインもあります。
ブドウの糖度以外に、アルコール度数に影響する要素とは?

原料となるブドウの糖度の他に、醸造方法や発酵期間もワインのアルコール度数に影響します。そのひとつが「残糖管理」と呼ばれる技術です。これは、アルコール発酵の進行をコントロールして糖分の残り具合を調整する方法です。
発酵途中に温度を下げて酵母の働きを弱め発酵を止めると、アルコールに変換されない糖分が残り、甘口のワインになります。一方で、糖分をすべてアルコールに変えるまで発酵を進めると(完全発酵)、辛口でアルコール度数も比較的高くなります。つまり、甘口より辛口のワインの方がアルコール度数は高くなる傾向があります。ただし例外も多く、高アルコールの甘口ワイン(アイスワイン、遅摘みワイン、酒精強化ワイン)、低アルコールの辛口ワイン(リースリングやヴィーニョ・ヴェルデなど)もあります。
酒精強化(フォーティファイドワイン)という方法では、発酵終了後にブランデーなどの蒸留酒を加えることでアルコール度数を高めます。ポートワインやシェリーがこれにあたります。
ワインの種類ごとの度数

白ワインのアルコール度数はおおよそ10〜13%、赤ワインは12〜15%程度とされており、一般的には赤ワインの方がやや高めです。ただし、赤ワインにはタンニン(渋み成分)が多く含まれるため、渋みとのバランスによって、実際に飲んだときのアルコールの感じ方が異なることもあります。ロゼワインは赤と白の中間的なスタイルで、アルコール度数も11~13%程度のものが多くみられます。
また、スパークリングワインは、瓶内やタンク内での二次発酵を経て造られるため、発酵の影響でアルコール度数がやや上がる傾向があります。日本で造られるスパークリングワインは、11〜12%が主流です。
アルコール度数別の適温

ワインは、それぞれの特徴に合わせた「適温」で飲むことで、より一層その魅力が引き立ちます。
アルコール度数が高いワインは、やや高めの温度で飲むのが適しています。たとえば、フルボディの赤ワイン(アルコール度数13.5%以上)は 16〜20℃ で飲むと、香りが豊かに広がり、味わいのバランスもよくなります。冷やしすぎてしまうと、タンニンの渋みが強調され、味が硬く感じられることがあります。(詳しくは:「フルボディ」とは?その特徴と楽しみ方 )
一方で、アルコール度数が低めのワインは、やや低めの温度で飲むのに適しています。ライトボディの赤ワイン(アルコール度数12%以下)は 12〜14℃ で飲むと、フレッシュな果実味が際立ちます。また、白ワインやスパークリングワインは 6〜12℃ が適温で、よく冷やすことで酸味が引き締まり、爽やかさがより際立ちます。
温度が高すぎるとアルコールの刺激が強くなり、香りや味のバランスが崩れてしまうことがあります。逆に低すぎると、ワインの繊細で複雑な香りを感じにくくなることも。せっかくの1本、温度管理にもひと手間をかけて、ワイン本来の美味しさを最大限に引き出して楽しみたいですね。
シーン別に楽しむ、低アルコールワインと高アルコールワイン

低アルコールワイン(5〜10%程度)は、軽やかで繊細な味わいが魅力です。日本ワインだと、軽井沢や北海道、山梨などの冷涼な気候で育ったブドウから造られ、エレガントで爽やかな印象の仕上がったワインが多いです。アルコールがあまり得意でない方や飲み慣れていない方にもおすすめで、サラダや魚料理などの軽やかなメニューと相性が良く、ランチや気軽な集まりの場にもぴったりです。
対して、高アルコールワイン(14〜17%程度)は、しっかりとした飲みごたえと深みのある味わいが特徴です。たとえば、樽熟成の甲州ワインなどが当てはまります。肉料理や煮込み料理などの重厚な料理とのペアリングに向いており、寒い季節やじっくりと味わいたいシーンに最適です。また、そのまま楽しむだけでなく、炭酸やジュースで割ったりフルーツを加えてカクテルにアレンジすると、飲みやすく見た目も華やかになり、いつもと違った楽しみ方もできます。
まとめ
ワインのアルコール度数は、単なる数字ではありません。それは、ブドウ畑での一年間の努力、醸造家の技術、そして自然の恵みが結実した結果です。つくり手を訪問するたびに感じるのは、ワインづくりは農業であり、工業であり、そして芸術であり科学でもある——まさに総合格闘技のようだということ。アルコール度数や糖度が高ければ良い、低ければ良いということではなく、何より大切なのは「ちょうど良いバランス」を見極めること。年に一度のワインづくりに懸ける人々の姿は、知れば知るほど深い尊敬の念を抱かずにはいられません。
ワインを楽しむときには、ぜひアルコール度数にも目を向けてみてください。そして、味わいだけでなく、その数字の向こうにあるストーリーにも思いを馳せながら、自分のペースで、思い思いの時間を楽しんでください。
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。