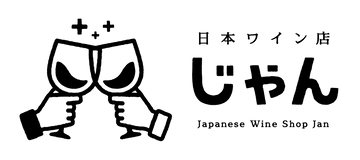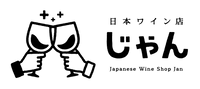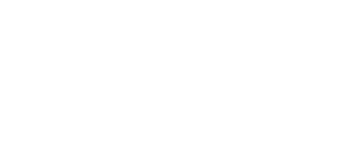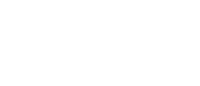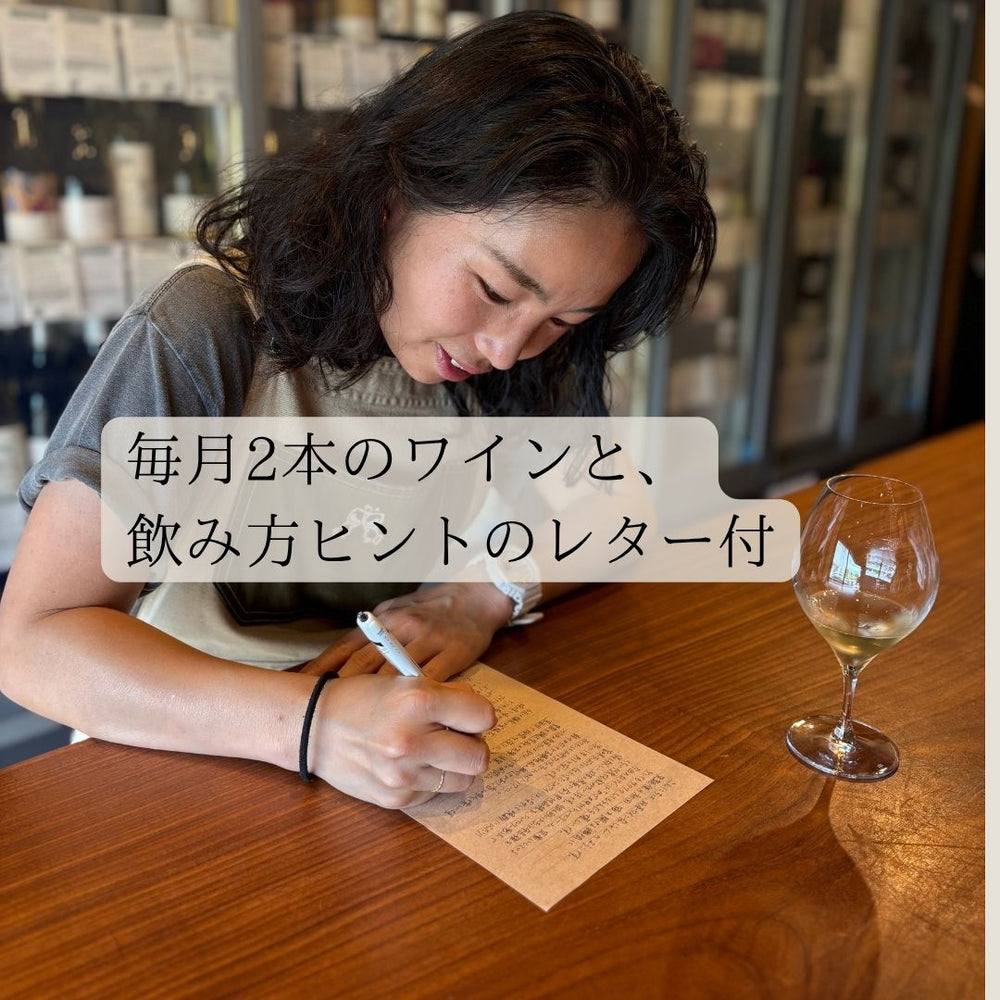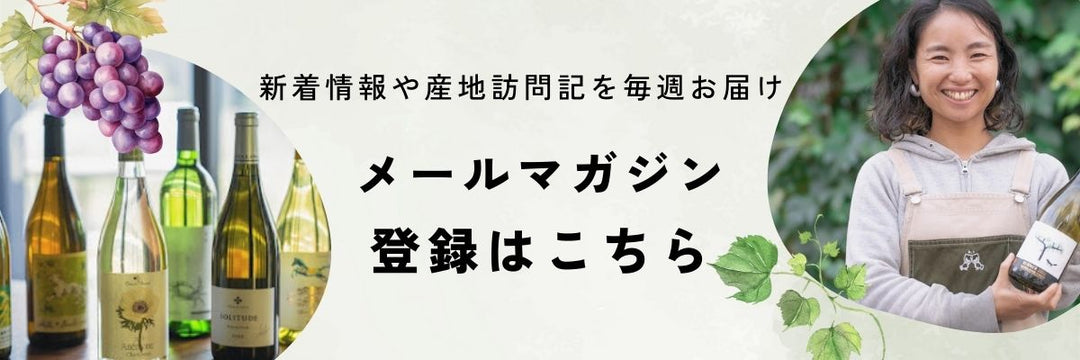ワインの「フルボディ」ってなに?その特徴や見分け方を解説
「フルボディってなに?」「重いって味が濃いってこと?」ワインの味わいを「重い」「軽い」と表現することや、「フルボディ」という言葉をなんとなく聞いたことはあるけれど、実ははっきりとは理解していない…そんな方もいるのではないでしょうか?この記事では、ワインの「ボディ」について、「フルボディ」「ミディアムボディ」「ライトボディ」の違いや見分け方を解説。日本ワインの中でも「重め」の味わいが楽しめるおすすめの銘柄もご紹介します。
目次
「ボディ」とは?ワインの味わいの指標

ワインの味わいを表す言葉の一つに「ボディ」があります。これはワインの「骨格」を示すもので、コクや力強さ、飲みごたえといった味の全体的な印象を表現しています。主に「酸(フレッシュさやキレ)」「タンニン(渋み)」「アルコール度数」「果実味」「ミネラル感」の5つの要素のバランスによって決まり、飲んだときの印象や余韻に大きく影響します。
「重い(重厚)」~「軽い(軽快、軽やか)」という軸で評価され、「フルボディ」、「ミディアムボディ」、「ライトボディ」の3つのタイプに分類されます。ボディはワインの飲みやすさにも関係するため、この感覚を知っておくと自分の好みに合ったワインや料理との相性が良い一本を選びやすくなります。
以下でこの3つのタイプの特徴をまとめていますが、「必ずこういうものだ」と決まっているものではなく、あくまでこういうものが多いという傾向としての分類です。それぞれのタイプを比較したときの相対的な違いとして捉えていただくとよいでしょう。
「フルボディ」とは?その特徴と楽しみ方

フルボディの赤ワインは、味わいが濃厚でコクがあり、アルコール度数はやや高め。タンニン(渋み)や力強さが際立ち、味わいだけでなく香りも豊かで重厚なのが特徴です。甘みが感じられ、酸は穏やか、まろやかな口当たりのものが多いです。飲みごたえがあり、余韻も楽しめます。人間の味覚では、酸が高いと軽く感じやすいため、酸が穏やかなフルボディは、相対的にまろやかに感じられる傾向があります。
代表的な品種にはカベルネ・ソーヴィニヨンやシラーがあり、深みのある味をじっくり味わいたい方におすすめです。適温は16〜18℃ほどで、冷やしすぎると渋みが強く出てしまうため注意が必要です。さらに、デキャンタージュやスワリング、熟成による味わいの変化が大きいのもフルボディの魅力。時間とともに表情を変えるその奥深さは、まさにワインの醍醐味といえます。
*デキャンタージュとは?
ワインを空気に触れさせ、香りや味わいをより引き出すために、ボトルからデキャンタと呼ばれる容器に移すこと。若いワインの風味をまろやかにしたり、熟成ワインの澱を取り除く目的もあります。
*スワリングとは?
グラスを軽く回してワインを空気に触れさせ、香りを広げる動作。飲む前に行うと、風味が豊かになり、より深い香りを楽しむことができます。
「ライトボディ」とは?
ライトボディの赤ワインは、濃厚で力強いフルボディとは対照的に、口当たりが軽やかで、さらっとした飲みやすさが魅力です。アルコール度数が低めのものも多く、ワインにあまり慣れていない方や、食前やカジュアルな食事に合わせて気軽に楽しみたい方にもおすすめ。渋みは控えめで、果実のフレッシュな風味に加え、キレのあるすっきりとした飲み口が特徴です。
代表的な品種にはピノ・ノワールやガメイがあり、特にボージョレ・ヌーヴォーなどの新酒では、ライトボディらしいフルーティーな口当たりとともに、その年のブドウの個性をストレートに感じられる楽しみもあります。飲みごろの温度は12〜14℃ほどとフルボディより低めですが、冷やしすぎないことで果実味や酸の鮮やかさが際立ちます。また、ライトボディのワインはフレッシュな味わいが魅力のものが多いため、開栓後はなるべく早めに飲み切るのが理想です。(こちらの記事もおすすめ:日本ワインの新酒とは?時期や特徴について解説!)
「ミディアムボディ」とは?フルボディとの違い
ミディアムボディのワインは、フルボディとライトボディの中間にあたり、バランスの取れた味わいが魅力です。適度な渋みがあり、フルーティーでありながらしっかりとした飲みごたえも感じられます。幅広い料理と合わせやすく、食事とともに楽しむことでその魅力がいっそう引き立ちます。代表的な品種にはメルローがあります。フルボディでは重たく感じるけれどライトボディでは物足りない、そんな時にちょうどいい選択肢となるのがミディアムボディです。
ボディで表現するのは赤ワインだけ?

「ボディ」という表現は、赤ワインによく使われます。赤ワインの多くは甘みを含まない辛口であるため、「甘口」「辛口」といった言葉よりも、渋みや酸味、コク、アルコール度数などを含めた全体的な重さや飲みごたえで味わいを表現する傾向があります。
一方、白ワインやロゼワインでは「甘口」「辛口」といった表現がよく用いられます。ただし、「ボディ」は赤ワインにしか使えないというわけではありません。すっきりと軽やかな白ワインを「ライトボディ」、コクのある白ワインを「フルボディ」と表現することもあります。
白ワインにもある、ボディの違い

フルボディの白ワインは、マロラクティック発酵や樽熟成を経て造られることが多く、クリーミーで濃厚な口当たりが特徴です。代表的な品種にはシャルドネやヴィオニエがあります。日本の甲州を使った白ワインにも、樽熟成などで重みを持たせたスタイルがあります。
一方、ライトボディの白ワインは、爽やかな酸味が際立つすっきりとした味わいで、よく冷やして楽しむのに適しています。ピノグリ(ピノ・グリージョ)やソーヴィニヨン・ブランなどが代表的です。(こちらの記事もおすすめ:ワインの製法「マロラクティック発酵」はどんな手法?その効果は? )
「ボディ」と「甘口・辛口」はどう違う?

「ボディ」と「甘口・辛口」は、どちらもワインの味わいを表す言葉ですが、意味することは異なります。
「ボディ」は、渋み、酸味、コク、アルコール度数などを総合的にみて、ワインの「重さ」や「飲みごたえ」を表現するものです。一方、「甘口/辛口」は、ワインに含まれる糖分(残糖量)による「甘さの度合い」を示しています。つまり、「ボディ」と「甘口/辛口」は別の尺度であり、必ずしも「フルボディ=辛口」「ライトボディ=甘口」などと決まっているわけではありません。
フルボディは甘口?辛口?

フルボディのワインでは比較的甘みを感じやすいですが、甘みを感じるのと「甘口/辛口なのか」はまた別のポイントです。フルボディのワインは、以下のような理由から甘みを感じることがあります。
● 豊かな果実味
完熟したブドウの濃厚でジューシーな風味が、甘さを感じさせます。
● アルコール度数が高め
アルコール度数が高いと口当たりがまろやかになり、甘みを感じやすくなります。
● 樽熟成の影響
樽由来のバニラやチョコレートのような香りが加わり、甘みのある印象を与えます。
ただし、ワインの「甘口・辛口」は残糖量によって決まるため、甘く感じても残糖が少なければ「辛口」と分類されます。一般的にフルボディのワインは辛口が多いものの、アマローネやポートワインのように甘口のフルボディワインも存在します。また、前述のとおり、ボディと甘辛は異なる尺度なので、「しっかりしたボディ=必ず辛口」というわけではありません。
ボディの違いはどう生まれる?味わいに影響する3つの要素
ワインの「ボディ」は、飲んだときに感じる重さやコク、飲みごたえといった印象を表す指標です。このボディの違いは、ワインの造り方に関わるいくつかの要素によって生まれます。
特に影響が大きいのは、「使われているブドウの品種」「アルコール度数」「熟成方法」の3つ。どれか一つだけでボディが決まるわけではなく、これらの要素が組み合わさることで、軽やかに感じたり、しっかりとしたコクを感じる仕上がりになります。
● アルコール度数
ボディに最も影響を与える要素がアルコール度数です。アルコール度数が高いとコクが強くなり重く感じられる一方、度数が低いと軽やかで飲みやすい印象になります。
● 使用されるブドウ品種
ブドウの品種や栽培環境もボディを左右します。果皮や種に含まれるタンニン(渋みのもと)が多い品種は、しっかりとした飲みごたえにつながります。特に、温暖な地域で育ったブドウは果皮が厚く、タンニンや果実味が豊富になるため、フルボディに近い力強い味わいになりやすい傾向があります。また、ブドウの糖度は発酵後のアルコール度数に影響します。糖度が高ければアルコール度数が上がり、よりコクのある仕上がりになります。
● 熟成方法
木製の樽で熟成させたワインは、ワインにコクや香りの深みが加わり、甘みを感じやすく飲み口がまろやかで重くなる傾向があります。こうした手法は、特にフルボディを目指したワインづくりでよく用いられます。一方で、新酒などはステンレスタンクで発酵・熟成されることが多く、すっきりと軽やかな味わいに仕上がります。
ボディの見分け方

ワインのボディの分類には、実は明確な基準があるわけではありません。ラベルにボディが記載されていることもありますが、これはあくまで造り手の判断によるもので、人によって感じ方が異なることもあります。たとえば、「ライトボディと書かれていたけれど意外と重く感じた」「フルボディなのに思ったより軽い」といったこともあるでしょう。
そのため、こうした表示はあくまで目安として捉えるのがよいでしょう。アルコール度数や使用されているブドウ品種をチェックすれば、ボディの傾向をある程度つかむ手がかりになります。
繊細さと力強さを併せ持つ、日本の「重め」ワイン
日本のワインは、高温多湿な気候や土壌の特性から「ライト〜ミディアムボディ」が主流です。「うす旨」や「出汁感がある」と表現されることも多く、海外のフルボディワインのような重さを感じるワインはあまり多くありません。その繊細でやさしい味わいは、素材の旨味を引き立て、和食との相性は抜群です。しかし近年では、醸し発酵や樽熟成といった手法を活かし、しっかりとしたボディ感を持たせた「重め」の日本ワインも登場しています。今回はその中からおすすめ3選をご紹介します。
● 401 桔梗ヶ原メルロ 2021
メルローに特化した塩尻のワイナリー、ドメーヌコーセイが手がける、豊かな果実味とエレガントな味わいの赤ワインです。アメリカンオーク樽で熟成されており、バニラのような華やかな香りが広がります。同シリーズには「401」の他に「503」「601」があり、いずれもメルロー100%で造られていますが、樽の種類によって風味の個性が際立ちます。601はフレンチオーク、503はアメリカンオークとフレンチオークのブレンドです。樽の違いを飲み比べて楽しむのもおすすめ。

豊かな果実味に樽由来のバニラがふんわりと香る、エレガントな赤ワイン
● 花菱 メルロー&カベルネソーヴィニヨン
「畑づくりの匠」が丹精込めて育てたブドウから造られた、力強く飲みごたえのある赤ワインです。豊かな果実味が際立つ味わいは、このワイナリーならではの特徴。収穫前のハンギングタイム(樹上で実らせる期間)を長く取るなど、土づくりから収穫のタイミングまでこだわって育てられたブドウを使い、果実の風味がぎゅっと凝縮された、濃厚で深みのある味わいに仕上げられています。メルローのやわらかな渋みに、カベルネ・ソーヴィニヨンのしっかりとしたコク、ほどよい樽の香りが全体をやさしく包み込み、バランスの取れた重厚な味わいが広がります。

ぎゅっと凝縮された果実味が際立つ、濃厚で深みのある赤ワイン
● 樽甲州
山梨県・塩山地区の古き良きワイナリーが手がける、アメリカンオーク樽熟成の甲州ワインです。黄金色に輝く美しい見た目に、とろみのある口当たり。甲州ならではのシャープなキレ味に樽熟成によるふくよかなコクが重なり合い、素晴らしいハーモニーを奏でる一本に仕上がっています。当店の角打ちでも非常に人気が高く、飲んだお客様の多くがボトル購入されていくほど。チーズや燻製ナッツと合わせてみてください。

甲州らしいシャープなキレ味と、樽熟成によるふくよかなコクが調和する白ワイン
まとめ:ボディがわかると、ワイン選びはもっと楽しくなる!

ワインの「ボディ」を知り、その違いや見分け方がわかれば、自分の好みに合った一本を見つけたり、料理とのペアリングを考えたりする際の大きなヒントになります。ラベルや説明だけではつかみにくかった味わいのニュアンスも、「ボディ」という視点から捉えることで、ぐっと選びやすくなるはずです。ワインを選ぶ際には、ぜひボディも意識してみてください。きっと、これまで以上にワインの楽しみが広がります。
「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。