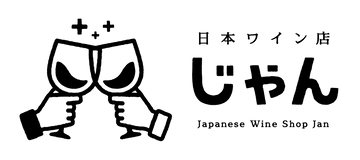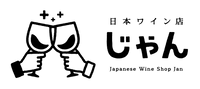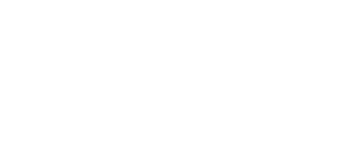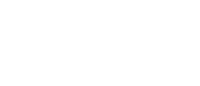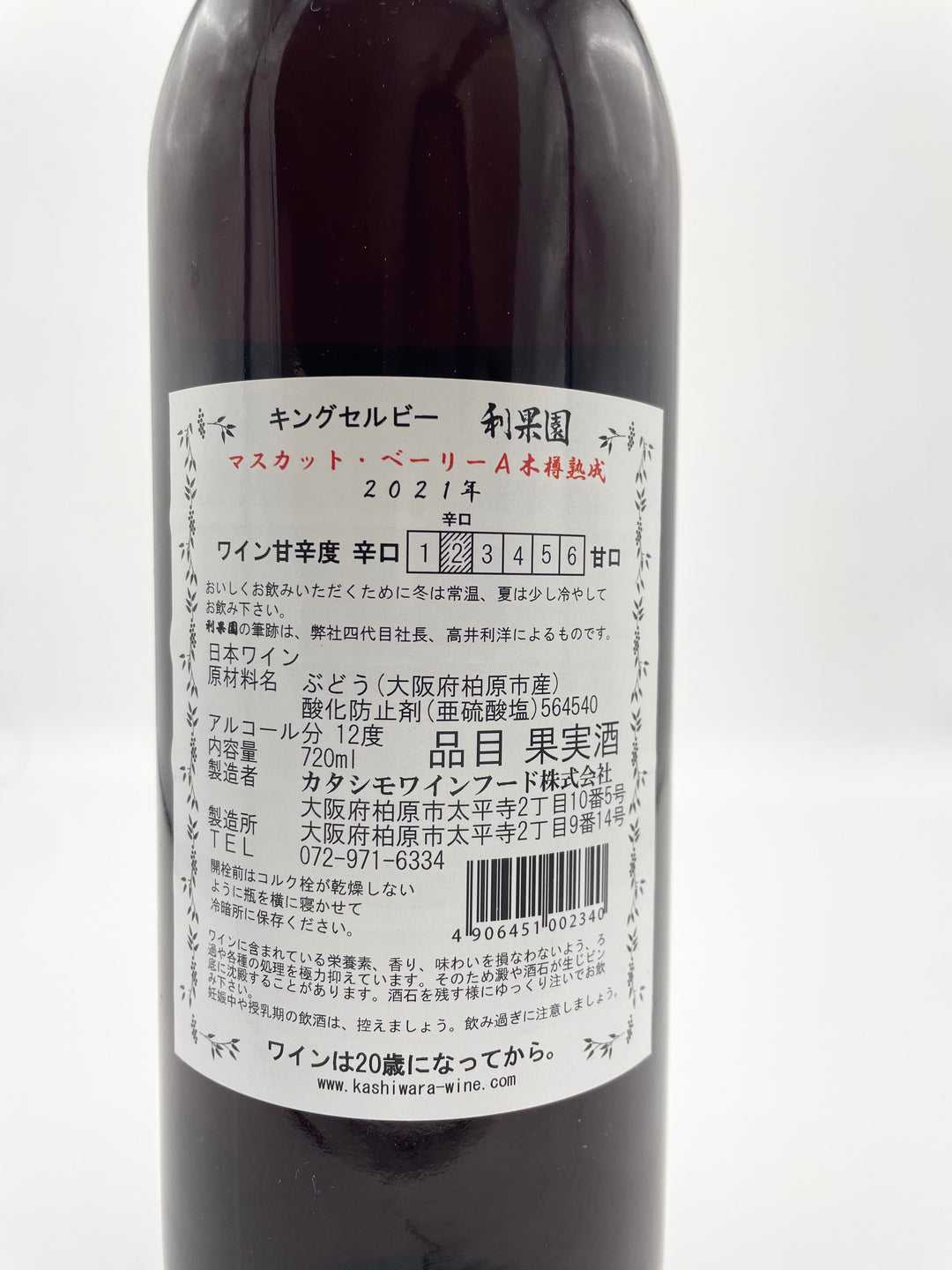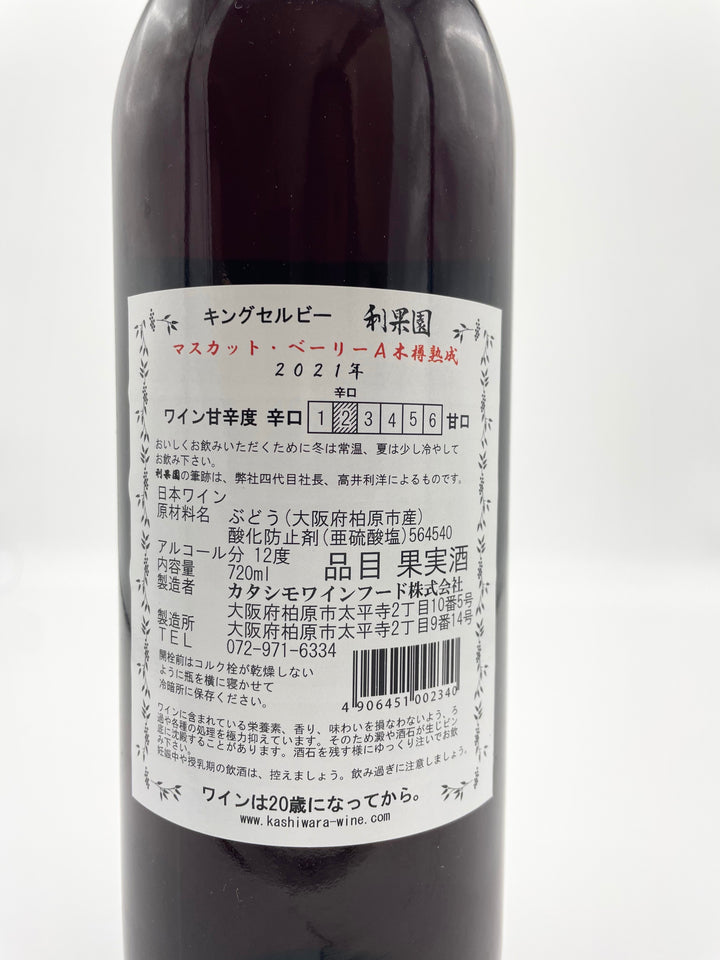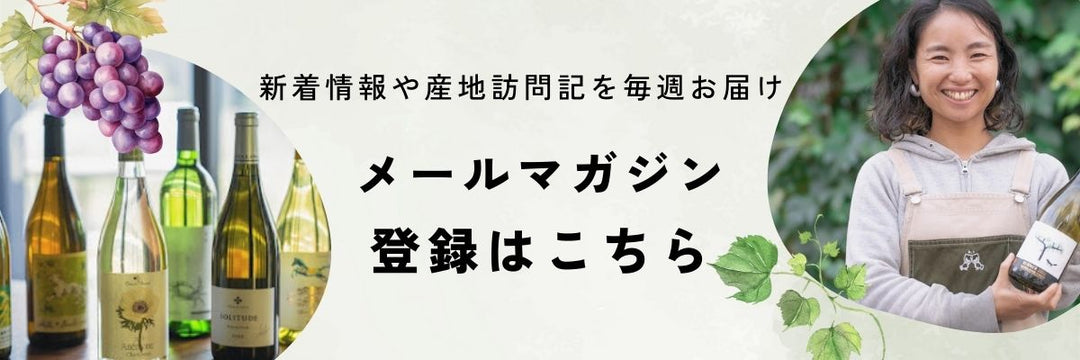カタシモワイナリー(大阪府)
利果園マスカットベーリーA
通常価格3,100円(税込)
3,100円(税込)
/
No reviews
6本セットと他の商品は同時に購入できません
【商品説明】
大阪の老舗ワイナリーがつくる、日本固有品種ブドウ100%の赤ワイン。フレンチオークで熟成されていて、落ち着いた樽の香りと共にちょうど良い渋みを味わえます。醤油や味噌を使った日本の食卓の料理にとても良く合います。和食と飲むとどこか懐かしさを感じながら、スイスイと心地よく流れてくれるワイン。一家に一本置きたい赤ワインです。
- タイプ
- 赤ワイン
- 産地
- 大阪府柏原市
- 品種
- マスカットベーリーA
- 味わい
- 辛口
- ボディ
- やや軽い
ご注文から1~3日以内に発送いたします。
発送先エリアにより送料が異なります。下の表でご確認ください。
1回のご注文でワインは最大12本まで発送可能です。
送料は決済時に自動的に計算されます。
また、5月~9月にお送りする商品は、雑貨・缶詰・瓶詰のみのお届けの場合を除きクール便での発送となり、380円(税込)のクール便代を送料に加えて頂戴します。
つくり手から預かった商品を、品質を損なわずお届けするためです。ご了承ください。
*発送先は沖縄県、離島を除く日本国内に限ります
| 発送エリア | 送料(税込) |
|---|---|
| 北海道/九州 | 990円 |
| 北陸/東海/信越/南東北 | 890円 |
| 中国/四国/北東北 | 960円 |
| 関東 | 860円 |
| 関西 | 930円 |